
脱サラ農業に関する書籍って、世の中にたくさんありますよね。
この類の書籍を150冊ほど読み、「なぜ会社員は農業を目指すのか?」を考えた時の文章がでてきたのでシェアさせていただきます。
もう10年前の拙い文章ですが、お役に立つポイントがあれば幸いです。
//この文章は2016年に執筆したものです。2016年時点の社会環境を前提としている点をご了承下さい//
3分で読めるまとめ
本論考の目的は、21世紀の「農」ブームを仕事観の観点から分析することで、現代日本人の仕事観を考える上での新たな示唆を得ることである。
序章では、現代日本人の仕事観を考える上で農という領域がいかに有効たりえるかを示している。現代「働く意味」が希求される時代であることをふまえ、21世紀になって急速に人々の注目を集めている仕事としての農に着目することが、どのような「働く意味」が求められているのかを明らかにする上で有効な視角であることを指摘する。
第1章では、仕事観に関する先行研究の整理を行う。第1節では「はたらくこと」を肯定的に意味づけようとする立場と、そもそも意味がないとする2つの立場を整理し、現代の日本人は「はたらくこと」を肯定的に意味づけようとする傾向にあることを指摘する。第2節では、高度経済成長期とバブル経済崩壊およびその退却と同一化した企業への貢献を目指す仕事観の一般期・多様期・過渡期では、企業の仕事環境と個人の価値観が密接にみられる。仕事を余暇の手段とみなし、報酬的な仕事観・自己実現を重視する仕事観に分類して整理する。第4節では、ポスト企業社会以降に出現した「やりたいことを仕事にする」といった脱物質主義的な仕事観をそれぞれ概観する。第5節では、先行研究で指摘されてきた仕事観を再度整理した後、農を通して仕事観を考えることの意義を求める。
第2章では、21世紀の「農」ブームがどのような歴史的背景の上に成り立っているのかを明らかにした後に、分析対象及び分析視角を提示する。第1節では、1990年代頃まで多くの人々にとって農という仕事が非現実的な選択肢であったこと、及びその認識に修正が加えられた「まなざし」を整理し、農を仕事として選ぶ人が増加したことを示す。第2節では、主に都市住民から農にむけられた「まなざし」を整理し、1960年代から70年代にかけて肯定的な価値を付与されたこと、一部はエコロジー運動等の社会運動と結びついたこと、そして1990年代以降には農村が消費の対象となっていったことを明らかにする。第3節では、本研究で分析対象とする「農業経営本」についてその概要を述べ、「農業経営本」は、一般の書店にて入手することができる「就農」や「仕事としての農の魅力」を題材とした書籍群の総称であり、非農家出身者を読者として想定したものである。第4節では、「農業経営本」を分析するにあたっての分析視角を提示する。先行研究において高度経済成長期以降の日本人にみられるものとして指摘された7種類の仕事観を基盤としながら、「農業経営本」の分析に即した形で7種類の仕事観を再構成する。
第3章では、第2章第4節で再構成した7種類の仕事観に基づいて「農業経営本」の言説分析を行う。第1節では「経済的な豊かさの追求を重んじる仕事観」について分析を行い、この仕事観が2008年から2010年の不況期に集中して見られる点などを指摘する。第2節では「余暇に対する手段としての仕事観」について分析を行い、この仕事観が『農業経営本』においてはほとんど見られない例外的な存在である点を指摘する。第3節では「自己実現を重んじる仕事観」について分析を行い、この仕事観が『農業経営本』の著者たちの主要な主張ではないものの決して軽視はされていない点を指摘する。第4節では「やりたいこと」を重んじる仕事観」について分析を行い、この仕事観が2000年代後半以降多数量される点、他の仕事観と共有することが多い点、他の仕事観よりも後ろの位 置にあることが多い点を指摘する。第5節では「スローな働き方を重んじる仕事観」について分析を行い、この仕事観が2000年以降コンスタントに見られるものでありながら、2000年代にはこの仕事観の意義自体は改めて問われることなく自明なものとされていたのに対して2010年代には様々な形で問われるようになった点を指摘する。第6節ではボランティアや社会運動など職業ではない「仕事」を通して実現される「他者の充足を重んじる仕事観」について分析を行い、農と社会運動との結びつきは確認されるものの、現代においては決して大きな動きとは言えない点を指摘する。第7節では「社会的ターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」について分析を行い、この仕事観が2010年代の『農業経営本』において支配的である点、物質主義に対しては忌避感を示しながらも、農の復興という使命感のためならば経済合理的な考え方を持ち込むことを厭わないというアンビバレントな性質をもっている点を指摘する。
第4章では分析結果をふまえ、「農」ブームにおける仕事観とは、「農」ブームから読みとくことのできる現代日本人の仕事観について考察を加えている。第1節では『農業経営本』に見られる仕事観を時系列に再検討する。そこで明らかになったのは、人々にとっての農は『田舎暮らし』のような消費の対象から、様々な意味を付与された「仕事」へと変貌しきたということである。2010年代のトレンドは、純粋な他者の充足志向でも経済的な豊かさ志向でもない、「社会的なターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」という“いいとこどり”の仕事観に行きついた。しかしその背後には、「やりたいこと」を重んじる仕事観が密に大きな影響力をもっていた。第2節ではこうした農に対する現代的な意味付与に逆行する流れである、「本質」や「本能」に働く自明性を求める言説の存在を指摘し、現代人の間で「意味づけへの疲れ」とでも言える現象が生じる可能性を検討している。
終章では、「農」ブームが示唆する仕事に意味を求めることの規範化は、それに翻弄される人々だけの問題だけではなく、農そのものの問題ともなりうることなどを指摘している。
序章 人々は「農」にどのような働く意味を求めるか
現代の日本において、仕事の意味が問われる機会は多い。例えば教育の現場では、「働く意味」や「働く理由」は重要な教育課題になっている。村上龍による『13歳のハローワーク』がブームとなったのは10年ほど前だが、現在では「キャリア教育」という言葉もすっかり定着した。テレビ、新聞などマスメディアにおいてもこのテーマは盛んに取り上げられており、また書店では「なぜ働くのか」、「働く意味」などがタイトルに入った書籍を数多く見かけることができる。大学生の就職活動シーズンにはこの種の出版が盛んに行われるほか、社会人向けのものであれ時期を問わず店の書棚を賑わしている。
この仕事の意味を問う傾向には2つの特徴がある(杉村2009)。第一には、仕事の充実を問めることの重要性が強調される点である。書籍を例にとると、「仕事とは自分の能力や興味、価値観を表現するものである。でなければ、仕事は退屈で無意味なものになってしまう」「意味のある仕事は自分自身が見つけなくてはならないのだ」といったように、こうした書物のほとんどにおいては自己の実現、自己の成長、社会への貢献、他者との絆などの様々な要素を通して仕事の充実を求めることが望ましいとされる。
第二には、働くことの意味が生きる意味と重ねあわされる点である。「働くことと、生きることの意味は働く喜びを得られるかどうかにかかっている」、「働くことは生きること」といったように、人生の充実は仕事の充実とともにあるとされる。仕事の充実が生き方を左右し、また仕事が生き方の体現であるとも考えられる現代の日本において、人々の仕事観と人生観とは密接に結びついていると言えるだろう。
しかし、この仕事に意味を求める傾向、そして仕事と人生を深く結びつける傾向には1つの問題点がある。それは、仕事の充実が容易に得られるものではない以上、多くの人々が不安に苛まれる危険性があるという点である。先に述べた自己の実現、自己の成長、社会への貢献、他者との絆などは、現実においては誰もが皆仕事を通して容易に実現できるものではない。しかし、「働くことは生きること」という規範を内面化した人々はそれを求めざるをえない。結果として、多くの労働者が不安を抱えながら自らの仕事と向き合うことになる。
このような状況のなかで人が仕事の充実を求める時、選択肢は大きく分けて2つあると考えられる。1つは現在の職業において仕事を充実させる術を模索しつづけるという道である。仕事を通した自己実現や「やりたいこと」の実現をテーマとした自己啓発本が描く模範的な生き方などがその典型であろう。そしてもう1つは新たな仕事に充実を求めるという道である。こちらは、自分が納得してできる仕事を求めてあえて正規雇用職に就かないフリーターや、脱サラなどがその典型であろう。そうして近年オルタナティブな仕事として人々の関心を集めている領域に「農」がある。
「農」に対するまなざしは1990年頃を境に大きく転換したと言われている。高度経済成長期以降人々はこぞって第一次産業から離れてゆき、稼げない農業は見捨てられるか、兼業農家として細々と継承されるケースが増加した。晴耕雨読の暮らしに対する憧れといった、漠然とした肯定的なまなざしは存在したものの、仕事としての農業は暗いイメージを伴っていた。しかし、90年代以降「田舎暮らし」や「ロハスな生活」が一部の都市住民の間で注目を集め、「農」のイメージは好転し始める。そして21世紀に入り、「農」を目指す人たちの裾野はさらに広がりを見せる。ビジネス誌や新聞、雑誌等のメディアで新規就農者の成功例が取り上げられることも増え、90年代には大型書店に赴いてようやく少し手に入る代物だった就農関連の書籍も今や同じ大型書店であれば数十冊が並んでいる。まだまだ小規模ではあるが、少なくともまなざしのレベルでは「農」ブームの様相を呈しているのではないだろうか。
メディアで扱われる「農」は、人々の需要をある程度反映したものであると考えられる。すなわち、「『農』がどのような意味をもつ仕事であると語られているのか」を明らかにすることは「メディアの受け手が『農』という仕事にどのような意味を求めているのか」を知る手がかりであると言えるだろう。そしてその作業は、仕事に意味を求める過程で発生する現代日本人の不安と苦悩をより鮮明に浮かび上がらせる一助となるという点において、意義のあるものと考えられる。
以上の背景をふまえ、本研究では第一に、「農」を語る言説のなかにはどのような仕事観があらわれるのかを明らかにする。第二に、「農」を語る言説のなかにみられる仕事観の変容を明らかにする。第三に、「農」を題材に仕事観を考えることが現代日本人の仕事観を考える上でどのような意味をもつのかを明らかにする。
したがって本研究の目的は、「農」ブームという現象を通じて、現代の日本人が「仕事にどのような意味を求めているのか」のその一端を解明することである。
第1章 仕事観の研究史
本章では、仕事観研究のレビューを通して、現代日本人に見られる仕事観がどのような歴史的背景の上に成り立っているのかを整理する。本論文は21世紀の「農」ブームを題材に現代日本人の仕事観の一端を明らかにすることを目的としたものであり、「農」に魅せられる人々の仕事観がこれまで語られてきた仕事観と比較してどのような特徴、新しさをもっているのかを明確にするためにもその歴史的変遷の把握は不可欠である。まず第1節では「仕事」「労働」といった働くことを表す言葉の定義に関する議論を踏まえた上で、近代における「はたらくこと」を肯定的に意味づける立場と、そもそも意味がないとする2つの立場を整理し、現代の日本人がもつ仕事観の多くは、「はたらくこと」を肯定的に意味づけようとするものであることを指摘する。第2節以降では、高度経済成長以降の日本人の仕事観を社会の変化に沿って整理することで、現代の日本人がもつ様々な仕事観はどのような歴史的背景の上に成り立っているのかを明らかにする。第2節では、高度経済成長期の「勤勉」「忠誠」を重んじ経済的な豊かさの追求と自己同一化した企業への貢献を目指す仕事観について整理する。第3節では、高度経済成長期以降の余暇が拡大した時期の、仕事を余暇のための手段として位置づける仕事観と、自己実現を重視する仕事観について整理する。第4節では、ポスト企業社会以降に出現した、「やりたいことを仕事にする」といった脱物質主義的な仕事観をそれぞれ概観する。最後に第5節では、先行研究で指摘されてきた仕事観を再度整理した後に、「農」を通して仕事観を考えることの意義を述べる。
第1節 「仕事」に対する意味付与を巡る2つの立場
本節ではまず「仕事」と「労働」の定義を巡る議論を整理し、次に「働くこと」を肯定的に意味づける立場と、「働くこと」にはそもそも意味が無いとする立場の2つの立場があることを明らかにする。そしてその上で、現代の日本人がもつ仕事観の多くは、「働くこと」を肯定的に意味づけようとするものであることを指摘する。
「仕事」あるいは「労働」という言葉は論じる人によって定義が異なっている。例えばアーレントは「仕事」を「人間存在の非生物性に対応する活動力」、「労働」を「人間の肉体の生物学的過程に対応する活動力」としている(Arendt 1958=1994:19-20)。仕事は価値を産み出す制作活動、労働は人間の生命の維持に必要な労苦、ということである。また宇野は、「仕事」を「稼ぎにはならないが、所属する共同体を維持するために必要な諸活動」、「労働」は「『仕事』と『稼ぎ(金銭的収入を得ることを目的とするもの)』と『暮らし(共同体の中で生きていくこと)』の総体」であるとした(宇野 2013)。アーレントは「仕事」と「労働」を並列に置づけたのに対し、宇野によると「仕事」と「労働」は包含関係にある。また、現代の日本人が一般的に想像する「仕事」は、アーレントの「労働」、宇野の「稼ぎ」に近いものであると言えるだろう。
このアーレントと宇野の両者はそれぞれ、「労働」と「稼ぎ」の拡大を批判する。アーレントは人間の様々な活動が必要物を確保するための(生計を立てるための)「労働」と標準化されてしまうことを批判し、宇野は「稼ぎ」に多様な社会的機能が集中しすぎた結果「稼ぎ」が機能不全をおこしたのが現代社会であると述べ、働きながら「仕事」や「暮らし」の要素を取り戻す別な方向性を模索する。これらの批判は、働くということが人間にとって大きな意味をもつようになってきたことに基づいていると言えるだろう。
元来それ自体に価値をもつものではなかった労働には、近代以降様々な意味が付与されてきた。古代西洋において労働は忌避されるべき活動であり、キリスト教にあっても労働は高い地位を与えられた活動ではなかった。しかし近代へと向かう過程においてはプロテスタントの勤勉と禁欲の倫理と結びついた労働は肯定的な価値を付与され(Weber 1905=2010)、マルクス主義の思想は人間の本質であるとして労働に喜びを見出した。また現代においても、労働は「自己実現の手段」「社会への貢献」など様々な形で意味づけられている。
こうした労働に対する意味付与に対しては、肯定的な立場と否定的な立場の両者が存在する(杉村 2009)。「労働の解放論者」と呼ばれる前者の立場の人々は、働くことの充実を求めることは大切だ、生きることの意味は働く喜びを得られるかどうかにかかっているといったことを主張する。一方で「労働からの解放論者」と呼ばれる後者の立場の人々は、「人間の意味が労働にあり、労働の意味(喜び)が人生の生きがいになるということは、労働が社会生活に必要であるということとは別個のイデオロギー的思い込みである」(今村 1998:150)、私たちが「労働」と呼んでいるものは「人類学的カテゴリーとしての、あるいは『額に汗して』生活必需品を生産する、人間の必要性としての『労働』とは選元できない」(ゴルツ 1988=1997:39)、「労働は、全体的で自律的な職人仕事の理想とは反対の極にある」(杉村 2009:37)というように、労働に意味を求めることに意味は無いとする。これをふまえれば、アーレントは「労働からの解放論者」、宇野は「労働の解放論者」ということになるだろう。
現代の日本では、「自己実現」「自己表現」「自己の成長」「社会への貢献」「他者との絆」など様々な形で労働に意味をもたせようという傾向が強く、教育、メディア、雇用形態など様々な背景が働くことの意味を求める方向に作用している(杉村 ibid.)。次節以降では、高度経済成長期以降の日本人の仕事観を概観していくことで、現代日本人のそうした仕事観がどのような歴史的背景の上に成り立っているのかを明らかにする。
第2節 高度経済成長期における日本人の仕事観
本節では、高度成長期に特徴的な日本人の仕事観を整理する。
企業社会の原型が形成された高度経済成長期においては、「忠誠」や「勤勉」を重んじる仕事観は日本人の労働を特徴づけるものであった(杜 2001)。この仕事観は、日本の仏教や儒教などの伝統文化に支えられたものであるとされている。例えば仏教では誰にも強制されることなく自分の意志で進んで役に立つということが大切であるとされ、儒教に基づいた社会風習である長幼の序の規定、男尊女卑、規律重視なども日本人の奥深くに根付いたものである(橋本 2009)。こうした伝統文化は、会社や組織に対する忠誠心や奉仕精神の土壌となった。
このような「忠誠」や「勤勉」を重んじる仕事観が高度経済成長期に出現したのは、企業が人々の生活を支える機能を十分に有していたからであった。この時期の日本人は終身雇用制、年功序列制といった日本的雇用の中で労働と生活を送り、先進国中で最長の労働時間のなかで「会社人間」と揶揄されながらも、経済発展による賃金上昇や手厚い福利厚生がそれを支えていたのである。
この時代における典型的な労働者は生活時間の多くを会社にコミットしており、働くなかで価値を見出していたのは、経済的な豊かさの追求と、自己同一化した企業への貢献である。
第3節 高度経済成長期終盤から80年代にかけての日本人の仕事観
前節では、高度経済成長期にみられる、忠誠や勤勉を重んじ、経済的な豊かさの追求と自己同一化した企業への貢献を目指す仕事観について整理した。代わって本節では、高度成長期終盤以降の余暇が拡大していく時期にみられる、仕事を余暇のための手段として位置づける仕事観と自己実現のために仕事をするという仕事観について整理する。
1970年代から1980年代にかけての仕事を巡る環境には三つの変化がある。第一に大企業で働く人を中心に余暇時間が増加したこと、第二に経済的な豊かさを手に入れた人が増加したこと、第三に能力主義管理という新たな労務管理法が登場したことである。能力主義管理のもとでは成果に応じて資源配分を受けることが公平とされるようになり、競争のなかで「過労死」「サービス残業」という言葉が生まれた(石田 1990)。
このような仕事を巡る環境の変化に伴い、大きく分けて2つの新しい仕事観がこの時期に誕生する。
1つめの仕事観は、仕事を余暇のための手段として位置づける仕事観である。ただし、この仕事観の出現は、2つの経路によっている。第一には、経済的な豊かさを手に入れた人々が旧来的な「仕事人間」のような働き方に批判的になった結果、余暇に対する評価が高まり、仕事はその余暇を楽しむ手段として位置付けたことによるものである。第二には、能力主義管理のもとで、待遇をめぐって格差が拡大する中でやりがいを感じられない人々が、仕事ではなく余暇を充実させることに人生の意義を見出し始めたことによるものである(安藤 1996)。そして、先述のような余暇時間の増加という環境の変化はこうした形での仕事観の拡大の下支えとなった。
このような仕事観は、余暇の性質の変化にも影響している。高度経済成長期において余暇時間の多くは「ラジオ、TVの視聴」「ごろ寝」といった労働の再生産のための「休息」に費やされたが、この時期になると「スポーツ」「旅行」「レジャー」といった「気晴らし」にあてられる時間が増加し(安藤 1996:77)、余暇における「自己開発」への期待も高まった(秋山 2004:27)。
第二には、自己実現を重視する仕事観である。能力主義管理のもとで労働は単に限定的・手段的に関われば済むものではなくなり、むしろ自己の「人格的能力」をも動員することによって遂行すべきものとなった(平川 1995:86)。ここで能力を思うように発揮できるような少数の人々にとっては、仕事は自己実現の場となるのである。
このように、高度経済成長以後の安定成長期において、一部の人々が「自己実現」のために仕事に適進していく一方で、大勢の人々は仕事は人並みにして余暇に生きる手応えを求めようとしていた時代であったと言える。
第4節 1990年代以降における日本人の仕事観
前節では、高度経済成長期以降仕事を余暇の手段として位置づける仕事観をもつ人が増加し、少数ながら自己実現のために仕事をするという仕事観をもつ人が現れたことを述べた。本節では、「やりたいこと」志向といったような心理的充足を重視するような仕事観が増加した背景にある環境の変化と、そのような仕事観の多様性について整理する。
それまでの安定した日本型経営が改革を迫られる90年代以降において、仕事をめぐる環境の変化には2点あげられる。第一には、日本型経営のさらなる揺らぎである。前節では高度経済成長期終盤に「会社人間」や「働きすぎ」への忌避感がみられたことを述べたが、90年代に入ると労働の個人化が進行した。従業員の会社帰属意識の低減は明らかに調査の結果に表れ、若者の間ではより自主的に仕事を選択しようという欲求、収入よりは仕事そのものがより大事なものであるという考え方が広まった。さらにバブル崩壊後には長期的な不況によって、日本型経営が不況から脱するのに無力であるという認識が定着した(杜 2001:45)。このような日本型経営の揺らぎは若い社員の間に「関係性の貧困」(前田 2010)を生じさせた。「イエ」や村落共同体に代わる擬似コミュニティとしての企業の性質は薄れ、同時に会社外のネットワークも希薄という状況の中で、若い世代はアイデンティティの危機に直面することになった。
第二には、消費の価値が減退したことである。飽和状態にあるモノに囲まれ、追い立てるようなトレンドにまつわる情報に揉まれ、人々の消費欲求それ自体が疑わしいものになっていき、人々にとって余暇に勢力をそそぎこむことが必ずしも自由を意味しなくなっていった(藤村 1995)。
日本的経営の下での使命感に満ちた働き方が求心力を失い、消費の意義すらも次第に説得力を持たなくなる時、人々にとっては物質的満足よりも心理的満足によって充足されることが重要となる。この価値観は「脱物質主義」と呼ばれ(間々田 2005, 2007)、人々の仕事観においても脱物質主義は重要なものとなる(寺崎 2009)。
寺崎(2009)は脱物質主義の仕事観は2つの極があるとしている。その一つは「やりたいこと」を仕事にしようとする仕事観である。この「やりたいこと」という表現には(1)「やりたいこと」ならば続けられる、(2)「やりたいこと」は今わからなくてもいい、(3)「やりたいこと」は他者とのコミュニケーションの中で徐々に形成されていくというより、既に自分の内部に存在しているので、自分の内部を探っていくことによってきっと見つかるはず、という想定を含んでいる(久木元 2009)。擬似コミュニティとしての企業も勤勉の報いを保証する宗教的超越者も経済的発展神話もはや存在せず、消費欲求も現実感がない中、若い世代は「やりたいこと」を「本当の自分」の中に求めるのである。
そして2つの極のもう一方は、自分の「やりたいこと」に合致する働き方を求めるのではなく、「仕事の中でゆっくりと自分の存在を確認する」(寺崎 ibid:65)ような仕事観である。地域社会で働き各々の「ローカル・アイデンティティ」を見出しながら「存在論的安心」を取り戻していく生き方もこれに該当する(宇野 2013)。
しかし、脱物質主義の仕事観は寺崎の指摘するこの2つの極に限定されるものではないだろう。90年代以降に特徴的な、物質的なものによる充足に重点をおかない仕事観には、次のようなものもあげられている。
1つは、ボランティアや社会運動といった広い意味での「仕事」を通した、他者への貢献を重んじる仕事観である。『仕事』が包囲されたただけではなく、「遊び」さえも包含される日本社会において、私たちの逃げ道はどこにも残されているのだろう」(藤村 1995:197)とした藤村は、90年代の日本社会にみられる可能性としてボランティアのような「職業としてではない『仕事』」(藤村 1995:198)を挙げており、ボランティア活動のみならず、地域自動加入団体の運営団体、社会運動などの「職業ではない労働」(秋山 2004:3)が自発性、働きがい、社会的な意義などを重んじた働き方であるという点で注目されている。
こうした労働の動機は「自分の経験や特技を活用したい」「社会の一員としての実感が欲しい」「義務なので仕方がない」「誰かに役立ちたい」「自分を含む世の中全体を良くしたい」など千差万別ではあるが、自己の充足以上に他者の充足を果たしたことによってその活動への従事が正当化されることが特徴と言える(秋山 ibid.)。
もう1つは、この他者の充足を重視する仕事観の異なった形態である。それは「ソーシャルアントレプレナーシップ」、日本語では「社会起業」と言われるものである。この社会起業とは社会問題の解決を市場原理のもとで図ろうとするもので、すなわち「社会をよりよくしよう」という使命感を持ち、従来のビジネス手法を積極的に取り入れながら新しい発想で経済的リターンと社会的リターンの両方を追求する活動であり、「自分のため」に働くのか「社会のために」働くのかが二者択一ではなく、むしろその両方が存在する仕事観であると言える(金子・田中 2009:107-109)。
第5節 先行研究における仕事観
第2節から第4節では、高度経済成長期以降の日本人の仕事観に関する先行研究を概観してきた。先行研究においては大きくわけて7つのタイプの仕事観が見られたが、本節ではそれらを今一度整理した後に、農業を通して仕事観を考えることの意義を述べる。
(1)自己同一化した企業への貢献を重んじる仕事観
第1のタイプは自己同一化した企業への貢献を重んじる仕事観である。このタイプの仕事観は、労働者の伸びゆく賃金、定年までの雇用、家族の生活などを企業が支えるという日本型経営が最も盤石であった高度経済成長期に特徴的なものであった。村落共同体や「イエ」に代わる擬似コミュニティとなった企業に対して労働者は自己同一化し、忠誠や勤勉の精神で以て企業に貢献することに働く意義を見出した。ただし労働者の企業への貢献は賃金および福利厚生と不可分なものであるから、この仕事観は経済的な豊かさの追求を重んじる仕事観と表裏一体の関係にある。
(2)余暇に対する手段としての仕事観
第2のタイプは仕事を余暇に対しての手段として位置づける仕事観である。この仕事観をもつ労働者は、仕事は人並みにこなしつつ余暇時間を重視し、そこに生きがいを求める。
この仕事観は、高度経済成長期が終盤を迎え多くの人々がある程度の経済的豊かさを享受することができた70年代から80年代にかけて特徴的なものであった。人々が余暇に対する志向を強めた背景には2つの仕事をとりまく環境の変化があった。1つは経済的豊かさがある程度達成されたことにより「会社人間」のような働き方が自明性を失ったこと、もう1つは能力主義管理による激しい競争のもとで待遇を巡る格差が拡大したことである。
(3)自己実現を重んじる仕事観
第3のタイプは、自己実現を重んじる仕事観である。ここでいう自己実現とは、自身の能力やパーソナリティーを仕事に注ぎ込み成果に反映させることを指している。高度経済成長期終盤に導入されはじめた能力主義管理のもとで、評価の基準は勤続年数から「よくできる」か否かへと移行していった。そのような評価基準のもとでやりがいを感じられる労働者がこの仕事観をもつようになったとされている。
(4)「やりたいこと」を重んじる仕事観
第4のタイプは、「やりたいこと」を重んじる仕事観である。この仕事観の特徴は「やりたいこと」は他者とのコミュニケーションを通して徐々に形成されていくというよりはむしろ「本当の自分」のなかに見つかるはずだと考える点であり、「やりたいこと」ならば楽しい、「やりたいこと」ならば続けられるという論理がはたらいている。この仕事観が特徴的にみられるのは、自己同一化した企業への貢献を重んじる仕事観、余暇に対する手段としての仕事観のいずれもが自明性を失った1990年代以降であるとされている。
(5)スローな働き方を重視する仕事観
第5のタイプは、スローな働き方を重視する仕事観である。この仕事観をもつ労働者は「やりたいこと」を仕事にしようとするのではなく、仕事の中でゆっくりと自分の存在を確認しようとする。この仕事観には合理性への対抗軸という意味合いもあり、都市を離れ、地域に根ざしながら存在論的安心を取り戻す働き方への志向も、この仕事観に該当すると言えるだろう。「やりたいこと」を重視する仕事観同様、1990年代以降に特徴的にみられる仕事観である。
(6)他者の充足を重んじる仕事観(職業としてではない「仕事」を通して
第6のタイプは、ボランティアや社会運動といった、広い意味での「仕事」を通して他者の充足を果たすことを重んじる仕事観である。この仕事観をもつ人々のなかには能力の発揮等の自己の充足を動機の一部とする者も存在するが、あくまで他者の充足に動機の軸足を置き、無償で活動に従事する点が特徴である。
(7)社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観
第7のタイプは社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観である。この仕事観をもつ労働者は、社会をより良いものにしたいという使命感と、その使命を仕事として成り立たせたいという思いの両方を併せもっている。「自分のため」に働くのか「社会のため」に働くのかの二者択一ではなく、その両者が併存する仕事観であると言える。社会起業やNPO法人と呼ばれるような働き方がこれに該当し、近年注目を集めている。
このように、高度経済成長期以降の日本人の仕事観は7つの類型に大別することができる。年代別にみると、高度経済成長期、そして高度経済成長期終盤から1980年代にかけては単一の仕事観が支配的であったのに対し、1990年代以降は多様な仕事観が存在することがわかる。しかし、先行研究では一般論として仕事観が多様化したことは明らかにされているものの、その意義に関しては言及されていない。
したがって、本研究では多様化する仕事観を「農」という1つの領域を通してより詳細に検討することを試みる。「農」を研究対象とする意義は2点ある。第一に、仕事としての「農」が近年になって大きく関心を集めているという点である。人々が「農」のどこに関心を寄せているかを検証することは、現代日本人の仕事観を考える上で示唆をもたらすものとなると考えられる。第二に、「農」と仕事観を結びつけた研究がほとんど存在しないという点である。この背景には、1990年頃までは農家の後継ぎでない人間が「農」を仕事にすることが制度上難しく、大多数の人々にとって「農」という仕事が現実的な選択肢になり得なかったという要因がある。
次の第2章では、「農」の実態および「農」にむけられた「まなざし」の研究を整理した後に、本章で扱った仕事観に関する先行研究を踏まえた分析視角を提示する。
第2章 「農」ブームの歴史的背景と分析視角
本章では、21世紀の「農」ブームがどのような歴史的背景の上に成り立っているのかを明らかにした後に、分析対象及び分析視角を提示する。まず第1節では、農政による制度改革を踏まえながら、1990年頃までは多くの人々にとって「農」という仕事が非現実的な選択肢であったこと、及びそれ以降には新たに「農」を仕事として選ぶ人が増加したことを示す。第2節では、主に都市住民から「農」にむけられた「まなざし」を整理し、1960年代から70年代にかけて肯定的な価値を付与されたこと、一部はエコロジー運動等の社会運動と結びついたこと、そして1990年代以降には農村が消費の対象へとなっていったことを明らかにする。第3節では、本研究で分析対象とする「農業経営本」についてその概要を述べる。第4節では、第1章での仕事観に関わる先行研究をふまえ、「農業経営本」を分析するにあたっての分析視角を提示する。
第1節 「農」をめざす人々の実態
本節では、高度経済成長期以降の日本において新しく農業に従事した人に関して、実態の面から整理する。
1990年頃になるまで、農家の後継ぎでない人間が農業に従事することは非常に困難であった。その背景には、日本における農地の非流動性がある。高度経済成長期以降、農政は一貫して構造政策を採り、農地の流動性を高めるべく農地の取得に関する規制緩和を行ってきた。1961年農業基本法¹¹、1980年の農用地利用増進法¹²、1992年の「新しい食料・農業・農村政策の方向の発表」(いわゆる「新政策」)、2009年の改正農地法など、農政は手を変え品を変え規制緩和を試みてきたが、制度の変更が実際の農地の取得しやすさに結びついたのは1992年の「新しい食料・農業・農村政策の方向の発表」を待たなければならなかった(野田 2005)。
1992年の「新政策」が農地の流動化に寄与したのは、同政策が農業労働力に関する認識を改めるものであったことによる。同政策以前では基本的に農家の長男だけが農業労働力とみなされていたのに対し、同政策においては女性、高齢者、非農家出身者らが新たに農業労働力としてみなされるようになったのである。農政のこの大きな方針転換には、農外への労働力の流出に歯止めがきかない状況下において、農業の非経済的価値を前面に押し出して「多様な担い手」を求めていかざるをえない背景があった(野田 ibid)。この時期を境目に新たに農業に携わる人間が増加に転じたことは統計からも明らかである。
次に、1990年代以前に就農した人々について整理する。先に述べた通りこの時期に就農したのは基本的に農業にルーツをもつ人々であるが、先行研究が明らかにしているのはその就農動機がきわめて現実的な問題によるということである。例えば1970年代前半頃の農業への還流労働力に論究したものとしては田代洋一(1976)、引田澄夫(1986)、中安定子(1995)等があり、中安は当時の農業への人口還流は景気変動によるもので、必ずしも「農業見直し」とは結びつかないことを指摘した。また、大友篤(1983)や山﨑亮一(2013)は1980年頃を境としたプッシュ・プル仮説¹⁴の終焉を述べ、社会経済要因よりも個人的ないし家族的要因による人口移動が主流となったことを明らかにした。近年のUターン移動研究としては江崎雄治(2002, 2005)のもの等が挙げられ、そこで江崎が指摘しているのは「実態を把握せず情緒的に捉えられてきた都市住民の農村志向」であり、Uターンを実行した者もしなかった者もその考えるきっかけは「親の面倒をみるため」という現実的な問題であったという。
一方で、1990年代以降に就農した人々は「後継ぎ」ではなく「担い手」と呼ばれ、生き方や自己実現の手段として農業を選択している新規就農者も多いことが指摘されている(江川 2000)。その他にも新規参入者がかかえてきた問題点を明らかにした斎藤和佐(1998)、農業者個々の生活過程を描き出した安藤義道(1999)、ライフコースの多様化を指摘した大内雅利(2000)、就農支援策を切り口とした中山智裕(1999)、岡部守(2001)、農協共済総合研究所・田畑保編(2005)など、新規参入者の実態に関しては数多くの研究が蓄積されている。
最後に新規就農者に関する近年の統計を概観する。2007年より開始された農林水産省による新規就農者調査によれば、新規就農者数¹⁵は近年横ばいかやや減少傾向にあるものの、非農家出身者である新規参入者数は増加傾向にある。特に40歳未満の新規参入者に限って言えば、2010年から2013年にかけて2.5倍となっており、大幅に増加していると言える。
図2 就農形態別新規就農者数の推移
(農林水産省『新規就農者調査』を元に筆者作成)
図3 40歳未満の就農形態別新規就農者数の推移
(農林水産省『新規就農者調査』を元に筆者作成)
また、新規就農者の就農実態に関する調査は平成13年を皮切りに平成18年、平成22年、平成25年に全国新規就農相談センターによって実施されており、新規参入者のなかでは若年層=経営志向、中高年層=生活志向という傾向が強まっていることが明らかになっている¹⁶。
本節では、高度経済成長期以降に新たに農業に従事した人々について、実態面から整理してきた。先行研究が示しているのは、1990年頃を境に就農者の質が転換していることである。1990年代以前の就農者は基本的に農家の「後継ぎ」であり、就農の動機は家族の事情等の現実的なものであった。一方で1990年代以降の就農者は「後継ぎ」に限定されない「多様な担い手」であり、そのなかには自律的に、各々の目的をもって就農しようとする人が多く含まれていた。同時の世代の就農が落ち着いた00年代中盤以降は新規就農者の総数は落ち着いているが、40歳未満の若い世代の新規参入者は大幅に増加している。したがって、1990年代以降の「農」ブームは、「農」と仕事が実際に結びついているという点で新しい性質のものであると言える。
しかし、晴耕雨読の生活への憧れといった「農」に対する肯定的なイメージは1990年代以前にも存在したようにも思われる。次節では、近年の「農」ブームが価値観レベルでも新しいものなのかを明らかにするために、「農」の実態ではなく「農」に向けられたまなざしに関する知見を整理してゆく。
第2節 「農」に向けられたまなざし
前節では、高度経済成長期以降の新規就農者について、実態の面から概観した。本節では、高度経済成長期以降に、「農」が肯定的にまなざされてゆく過程を概観する。
戦後しばらくの間、「農」が営まれる場である田舎は否定的に語られていた。戦前の土着の文化への思いが「農本主義」や「日本主義」としてファシズム体制に結びついたため¹⁷、その後進性が問題視されたのである(塚本 1991)。
しかしこうした否定的なまなざしは1960年代を境に大きく転換していく。流行歌における「地方」の歌われ方を研究した見田(1978)や1963年に始まったテレビ番組『新日本紀行』を研究した石井(2007)は、この時代に日本の農村はただ抽象的な「自然の風物」として見られるようになり、合理主義や物質主義への対抗軸として肯定的な価値を付与されたことを明らかにした。
1970年代には、農村は「自然豊かなユートピア」以上の意味をもつようになる。1970年に始まった国鉄のディスカバー・ジャパン¹⁸キャンペーンは一斉を風靡したが、同キャンペーンにおいて「ふるさとの発見」は「私の発見」と結びつけられていた。これは、消費の場を通じてもアイデンティティが希求されるような社会へと移行したことの表れであると言えよう¹⁹(石井 ibid)。
また、「農」がもつ合理主義や物質主義への対抗軸としての側面は、1970年代にはエコロジー運動という形でも現れた。工業化の初期に起こった労働者を主体とした社会運動に対しエコロジー運動は「新しい社会運動」²⁰と呼ばれ、企業が生みだす環境破壊を批判した運動家たちは有機農産物を求め、大企業に頼らない生き方として生協を盛り立てた(小熊 2013)。
しかし、こうした「エコロジー」や「有機農業」といった方向性に対しては、戦前と同様の「工業や商業と対比して農業の特徵を炙り出す」という種の被害者意識でしか農業の存立意義をみいだせないような思考であるとして、その危うさが指摘されている(藤原 2013)。
一方で、「農」に対するまなざしの変容が本格的に生じたのは1990年頃であるとの立場も存在する(立川 2005、矢部 2005、秋津 2007)。行政のまなざしの変容という点では、前節でも述べた「新しい食料・農業・農村政策の方向の発表」(1992年)の存在が大きい。この「新政策」において農政は農村=農業生産の場という認識を改め、「農」の様々な社会的機能を強調することで、高齢者、女性、非農家出身者などの関心を集めることを画策した。また都市住民、消費者のまなざしという視点では、この時期田舎暮らしやグリーンツーリズムといった農的なものに対する需要が本格化し、田舎暮らしやアウトドア関連書籍の隆盛がみられるのも1990年代中ごろである。よって、1990年代には「農村空間の商品化」が生じたと考えられている(立川2005)。
各種メディアで描かれる「農」に関する先行研究では、農業自書の記述を分析した長井淳(1996)、風景画での農村風景の構成要素を扱った森義憲・ほか(1999)、戦後から現在にかけて小学校社会科教科書における農業・農村の取り上げ方を分析した北口まゆ子・広田純一(2000)などがあるが、これらは一般的な都市住民の仕事観と直接的に結びつくようなものではないだろう。
よりポピュラーなメディアを分析対象としたものには、1970年代から2000年代前半までの「農」をテーマとしたマンガを分析した一宮(2008)がある。一宮によれば、80年代までのマンガにおいては農業・農村が「社会問題」もしくは「カッコ悪い」存在としてネガティブな側面から表象されていたのに対し、80年代後半からは有機農業といった農業のオルタナティブな側面が、90年代以降は都市と対等な存在としての農村が描かれるようになったという。
本節では、高度経済成長期以降の「農」に向けられたまなざしを概観した。先行研究からは、高度経済成長期以降に「農」のイメージが好転した要因には2点あると言える。第一には、人々にとっての「農」が必ずしも故郷と結びつくものではなくなり、抽象的な「自然」へと変化していった結果、農村社会の前近代的な負のイメージが薄れた点があげられる。
第二には、高度経済成長により多くの人々がある程度の経済的豊かさを享受した結果、合理主義や物質主義への反省がみられるようになった点があげられる。「農」のもつ牧歌的なイメージが、合理主義や物質主義の対極にあるものとして肯定的にとらえられたのである。
また、そうした反省の一部は、エコロジー志向、有機農業志向という形で社会運動ともなった。こうした運動は、工業や商業と対比させる形で「農」の本質的な価値を主張するという点で戦前の農本思想と共通する部分もあり、「農」がそのような性質を帯びやすいという点には留意しておく必要があるだろう。
1990年代に入ると、グリーンツーリズムや田舎暮らしが注目を集めた。これは「農」に対する単なる「憧れ」やディスカバー・ジャパンキャンペーン流行させた「旅行」よりも、より「農」との関わりが強いものであると言えるだろう。そしてそれを可能にしたのは、農政側の認識の変化であった。
しかしグリーンツーリズムや定年後の田舎暮らしは農村空間の「消費」という意味合いが強く、21世紀に入って持て囃されている「仕事としての『農』」とは様相が異なる。そこで本研究では「仕事としての『農』」を扱った一般人向けの書籍群を分析対象とするが、そうした書籍群については次節で詳細に述べることとする。
第3節 農業経営本
本節では、本研究で分析対象とする「農業経営本」の定義、「農業経営本」を分析対象とする意義、そして「農業経営本」の概要について述べる。
現在書店では「農」に関する書籍を多数見かけることが可能である。学術書、農家向けの技術指南書、ビジネス書など様々なジャンルの「農」を題材とした書籍が存在するが、「就農」や「仕事としての『農』の魅力」を唱うものは、大型書店においては新書・ハードカバーを問わず「農業書」という棚割に分類されている。よって、これらの書籍群のうち、(1)「就農」や「仕事としての『農』の魅力」を題材とし、(2) 非農家の人々を読者として想定しており、(3) 学術書でないものを「農業経営本」と呼ぶことにする。
次に、「農業経営本」の読者には誰であろうか。2015年7月8日時点で、紀伊國屋書店梅田本店には30冊以上の「農業経営本」が陳列されている。2014年の新規参入者数が年間約2900人に過ぎないことを考慮すると、「農業経営本」の読者は現実的に就農を検討している人々には留まらないだろう。「農」に関心のある人々、脱サラを視野に入れた段階の人々など、幅広い読者層をもっていることが想定される。
それでは、仕事観を考える上で「農業経営本」を分析対象とする意義は何か。それは、「農業経営本」が「農」に関心をもつ人々の仕事観を映す鏡になると考えられる点にある。「農業経営本」はその時々の人々の需要をある程度想定した上で刊行されていると考えられる。よって農業経営本における仕事としての「農」に関する記述は、読者が「農」という仕事に期待していること、より一般化すれば読者の仕事観に沿うものになっている可能性が高い。したがって、「農業経営本」の分析は、「農」に関心をもつ人々の仕事観を検討する上で有効な視座となると考えられる。
以上をふまえ、本研究における分析対象資料の抽出は以下のように行った。まず、「農業経営本」にあたる書籍がカテゴライズされている「国立国会図書館サーチ」の分類記号「611:農業経済」²³のうち、2000年から2014年に出版された4560冊をピックアップした。次に、「農業経営本」の条件にあてはまるもの158冊をピックアップし、そのなかから紀伊國屋書店およびジュンク堂書店のデータベース上に存在しない2冊は一般的には手に入らないものとみなし、除外した。よって計156冊が今回の分析対象資料となり、年度別の集計結果が図4である。
(図表)
図4 農業経営本の刊行数
『農業経営本』の刊行数は2009年にピークを迎えた後、一度減少し、2014年に再び増加している。また、2015年では6月末までの半年で9冊が刊行されているため、2014年の増加は一過性のものではないと考えられる。
本節では「農業経営本」の定義、分析の意義、および「農業経営本」の概要について整理した。次節では、「農業経営本」の分析視角を述べることとする。
第4節 分析視角
次の第3章では「農業経営本」を仕事観の観点から分析するが、それに先立って本節では、第1章で整理した先行研究をふまえ分析視角を提示する。
先行研究で得られた知見に基づくと高度経済成長期以降の日本人の仕事観を7種類に大別することができるのは、第1章第5節で述べた通りである。しかし、その7種類の仕事観のなかには、「農」という領域を考える上でそぐわない点が存在する。したがって、基本的にはその7種類の仕事観を踏襲しながらも、一部変更を加え、本研究における分析視角として再構成する。
(1)経済的な豊かさの追求を重んじる仕事観
第一の仕事観は、「経済的な豊かさの追求を重んじる仕事観」である。この仕事観をもつ人々は、多くの収入を得ることを目指し、ビジネスのチャンスがあれば積極的にものにしようとする。高度経済成長期においてこの仕事観は「自己同一化した企業への貢献を重んじる仕事観」と表裏一体であったが、「農」の領域ではそのような「会社人間」的な働き方は見られないものと思われる。
(2)余暇に対する手段としての仕事観
第二の仕事観は、「余暇に対する手段としての仕事観」である。この仕事観をもつ人々は、仕事に対して積極的に意味づけを行うことはせず、仕事は人並みにして余暇時間を充実させようとする。
(3)自己実現を重んじる仕事観
第三の仕事観は、自己実現を重んじる仕事観である。この仕事観をもつ人々は、自身の能力やパーソナリティーを仕事に注ぎ込み成果に反映させること、仕事を通して自律感や有能感を感じることに働く意味を見出す。
(4)「やりたいこと」を重んじる仕事観
第四の仕事観は、「やりたいこと」を重んじる仕事観である。この仕事観をもつ人々は、仕事が自身のアイデンティティと一致することを重視する。すなわち、自身が好きなこと、楽しいと思えることを仕事にすることを重視する。
(5)スローな働き方を重んじる仕事観
第五の仕事観は、スローな働き方を重んじる仕事観である。この仕事観をもつ人々は、仕事の中で、あるいは仕事を通した社会的アイデンティフィケーションの形成を通して、ゆっくりと自分の存在を確認しようとする。
(6)他者の充足を重んじる仕事観(職業としてではない「仕事」を通して)
第六の仕事観は、ボランティアや社会運動といった、広い意味での「仕事」を通して他者の充足を果たすことを重んじる仕事観である。この仕事観をもつ人々のなかには能力の発揮等の自己の充足を動機の一部とする者も存在するが、あくまで他者の充足に動機の軸足がある。
(7)社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観
第七の仕事観は、社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観である。この仕事観をもつ労働者は、社会をより良いものにしたいという使命感と、その使命を仕事として成り立たせたいという思いの両方を併せもっている。「自分のため」に働くのか「社会のため」に働くのかの二者択一ではなく、その両者が併存する仕事観であると言える。先行研究ではこの仕事観を体現する働き方として社会起業やNPO法人があげられていたが、個人事業主であってもこの仕事観をもつものはいるだろう。
以上 7 種類の仕事観を、「農業経営本」の分析視角として用いる。これらは完全に排他的ではないが、これは本研究が仕事観の研究史における類型性をより重視していることによる。
また個人が複数の仕事観を有するのも自然なことであると考えられる。事実、一冊の「農業経営本」のなかには複数の仕事観が記述されている場合がほとんどであるが、そこに軽重はあるだろう。そこで本研究では、各「農業経営本」の「はじめに」ならびに「おわりに」に該当する箇所で言及されている仕事観を、著者が強調したであろう仕事観とみなすこととする。
また、補助的な分析視角として、以下の要素群を用いる。これらは、各「農業経営本」においてどのように「農」が取りあげられていたか、またどのような要素が用いられていたかを示すものである。[自然・環境]から[生まれ]までの要素群は、表1でも取り上げた就農実態調査の調査項目を基にしたものであり、[農業保護]および[その他]の要素群は、筆者が付け加えたものである。
[自然・環境]【農業が好き】【自然や動物が好き】【農村の生活(田舎暮らし)が好き】
[安全・品質]【食べ物の品質や安全に興味】【有機農業をやりたい】
[家族・自由]【時間が自由】【家族と一緒に仕事ができる】【子供を育てるには良い環境】
[経営]【自ら経営の采配を振れる】【やり方次第で儲かる】【以前の仕事の技術を生かす】
[消極的]【サラリーマンに向いていない】【都会の生活に向いていない】
[生まれ]【配偶者の実家が農家】【農家の跡取りだった(実家が農家)】
[農業保護]【耕作放棄地問題】【後継者問題(産地を守る)】【食料自給】
[その他]【夢・ロマン】【ノスタルジー】【人間の原点としての農】【「つくる」ということ】【身体性】【物質主義への忌避感】
次章以降では、本節で述べた7種類の仕事観および補助要素群に基づいて、分析・考察を行ってゆく。
第3章 「農業経営本」の言説分析
本章では、第1から第7の各節において、第2章第4節で提示した7種類の仕事観に基づいて「農業経営本」の言説分析を行う。同じく第2章第4節で提示した補助要素群については、適宜使用していくものとする。
第1節 経済的な豊かさを追求する仕事観
本節では、「農業経営本」にみられる「経済的な豊かさを追求する仕事観」について分析を行う。この仕事観をあらわす典型的な言説には、以下のようなものがあげられる。
実際、みんながみんな農業に魅力を感じて、わっと集まってしまえば、競争が激しくなり、さらに生き残るのも大変になる。だが、いまのところ多くの人間が農業にドドドっと駆け寄ってくる様子はない。特にコメ農業には……。これはメチャメチャチャンスである。しかもこれだけ巨大な可能性が眠っているビジネスはほかにない。(長田 2008:7)
変革が進んでから参入するのはあまり得策ではない。今ならまだ先行業エリートを享受できる。チャンスである。(中略)農業は“儲かる”ビジネスである。(ダイヤモンド 2009:238-239)
この仕事観が「はじめに」や「おわりに」内にあらわれる「農業経営本」において、「農」はビジネスチャンスとして捉えられるケースがほとんどである。本稿においても、「農」という領域がいかにビジネスとして発展可能性の視点導入することでどれだけの利益をあげられる可能性が眠っているか、と書き記されている。一冊を通してみても【農業が好き】【自然や動物が好き】【農村の生活(田舎暮らし)が好き】といった要素群についての言及がないものが多く、以下のように、この仕事観をもつ著者にとって「農」は様々な産業のなかの1つなのである。
しかし、経営には法則がある。農業だけが特別ではない。それに基づいて、農業の特殊性に注意しながら創意工夫を凝らせば、成功する確率は高くなるはずである。(山下 2010:9)
私は、農業(特に有機農業)ほど、可能性を秘めた産業はないと思っています。(中略)私が2000年に就農して以来、農業に携わっていて感じるのは、農業も他の産業も同じだということです。「しっかりと生産を行って、販売先を開拓する努力を続けていく」こと。それは自動車メーカーや飲食店など、他の産業となんら変わりありません。(松木 2010:3)
しかし意外なことに、この仕事観と「自己実現を重視する仕事観」が共存することはほとんどない。【自ら経営の采配を振れる】【やり方次第で儲かる】といった自己実現の要素は本編には見られるものの、「はじめに」や「おわりに」のなかでこの仕事観と同時に語られるのは、以下のような『やりたいこと』を重んじる仕事観なのである。
これからの農業はもっと幅広く捉え、もっと自由に、そして楽しくおもしろくやっていくべきだと私は感じている。(長田 2008:6)
東京のレストランで働いていた最後の1年間は、仕事以外に何か面白いことはないかと、そればかりを考えていました。釣りやキャンプ、野球、サッカーなど、趣味に楽しみを求めていたのです。しかし今は仕事と遊びの境目がありません。仕事を人生最大の遊びにできたことは、本当に幸せなことだと思っています。(松木 2010:202)
このように、経済的な豊かさを求めながらも、「仕事と遊びの特殊な接合」(牧野 2015:87)が望ましいとされるのである。これは、「余暇に対する手段としての仕事観」とは対照的な仕事観と言えよう。
しかし、この「経済的な豊かさを追求する仕事観」は、第2章で明らかにした「農」の脱物質主義的な性格とは対照的に見える。ここで、この仕事観を含む『農業経営本』が刊行された年次に注目してみると、ほとんどが2008年から2010年に集中しており、刊行数が再び増加した2014年には1冊しか出ていないことがわかる。これはサブプライムローンに端を発する不況の底の時期と重なっている。ここからは、深刻な不況の際には、対照的な性格をもつ「農」とさえ結びつくほどに経済的な豊かさが希求されるということが推察されるのではないだろうか。
第2節 余暇に対する手段としての仕事観
本節では、「農業経営本」にみられる「余暇に対する手段としての仕事観」について分析を行う。ただし、この仕事観に合致する言説は1冊においてしか確認することができなかった。
馬頭の自然のなかで過ごす気持ちよさは、仕事のやりがいや収入の多さといった魅力をはるかに凌いでいたし、息子を育てるなら田舎の方がいいという確信もあった(樺島 2004:34)
『田舎暮らしをする限りは有機農家をめざす』というような大志は抱いていない。そんなことをしたら、すぐに食い詰めてしまうのが目に見えている。プロの農家でさえ農業で喰っていくのは大変なのに、技術もない素人の私がやれるはずがない。(樺島 2004:41)
この著者はただただ田舎での生活に憧れており、年間300万円程度稼ぐことができればどんな仕事でもよいというスタンスをとっている。これは『農業経営本』においては例外と言ってよいだろう。
第3節 自己実現を重んじる仕事観
本節では、『農業経営本』にみられる「自己実現を重んじる仕事観」について分析を行う。この仕事観をあらわす典型的な言説には、以下のようなものがあげられる。
みんながうらやむ正しい進路などはっきりした今、若者は好きなことをとらぬき、自分の頭と手で考え、時代を切り開かねばなりません。農業は、それを小規模でも実現できる、数少ない仕事の一つです。自分の思い通りにならない条件の中で勝機を見つける、知的でクリエイティブな農業の魅力が伝わることを願っています。(久松 2014:10)
『好きなことをつらぬき』とあるようにこの言説は『やりたいこと』を重んじる仕事観をあらわす言説でもあるが、頭を使って能力を発揮することを説いているため『自己実現を重んじる仕事観』をあらわす言説でもある。しかし、この仕事観は『農業経営本』における主要な主張であるとはほとんどみられない。
ただし、この「クリエイティブ」という言葉は本編においては頻繁に使用される言葉である。農家が各自工夫を凝らし、その創意工夫が農作物に反映されるという点で農業が非常にクリエイティブな営みであることには疑いの余地はないだろう。多くの『農業経営本』がこの点に言及している以上この仕事観が決して軽視されているわけではないと考えられるが、『農業経営本』の著者たちが『はじめに』や『おわりに』で読者に強調して伝えたいのは、「農」という仕事がもつ他の側面なのだと思われる。
第4節 「やりたいこと」を重んじる仕事観
本節では、『農業経営本』にみられる「やりたいこと」を重んじる仕事観について分析を行う。前章で述べたように、この仕事観をもつ人は「本当の自分」のなかにある好きなこと、楽しいと思えることを大切にしているのであった。この仕事観をあらわす典型的な言説には、以下のようなものがある。
楽しい農業を実現するにはどうしたらよいのか?(杉山 2005:4)
明日のお米を心配しなければいけない。そんな状況であっても、独立した時に決めた「やりたい(情熱を傾けられる)仕事だけをやる」という自分のルールにはこだわっていた。(加藤 2010:22)
ビジネスの手管だけで生き残れるほど、農業は甘くありません。
「やりたいんだよ!」という消えることのない情炎が腹の底になければ、どんな風を送っても強い炎を燃やし続けることはできないのです。
(久松 2014:8)
このような「やりたいこと」にこだわる記述、あるいは楽しい仕事であれば続けられるという記述は、2000年代後半以降の『農業経営本』にもいくつも実に多数存在する。ここからは「『やりたいこと』にこだわる仕事観」が近年非常に求心力をもっていることが伺える。
またこの仕事観は多数みられるため、必然的に他の仕事観と共存することが多くなるが、ここで注目すべきはその前後関係である。すなわち、この仕事観は「経済的な豊かさを追求する仕事観」、「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」といった他の仕事観より“後ろ”で語られるのである。以下に一例を示す。
いや、見方とか考え方とか、むずかしい話はいい。とにかく土と戯れるのはほんとうに楽しいし、心の底から爽快な気分になれるから。
(永島 2012:7)
その時に気づきました。そうか、自分はアホなんだと。そのズッキーニが採れる頃には、お客さんはいないかもしれないのです。でも、楽しい。普段は、お客さんに尽くすのが仕事だの、経済合理性だの言っているのに、根本のところでは、ただ農作業がしただけだったのです。
(久松 2013:160)
このように、楽しさと結びついた「やりたいこと」は、他の「働く意味」と比較してより説得力をもつものとして語られるのである。このことからもこの仕事観が近年非常に求心力をもっていることが伺える。
第5節 スローな働き方を重んじる仕事観
本節では、『農業経営本』にみられる「スローな働き方を重んじる仕事観」について分析を行う。スローな働き方とは、仕事の中で、あるいは仕事を通した社会的アイデンティフィケーションの形成を通して、ゆっくりと自分の存在を確認しようとするような働き方であり、合理性への対抗軸としての側面ももつものであった。この働き方をあらわす典型的な言説には、以下のようなものがある。
誰もが一度はもったことのある「田舎でのんびり暮らしたい」という夢(田舎暮らし研究会 2002:22)
自分ひとりで生きようとするのではなくて、常に誰かとのかかわりの中で、ともに生きようとする、そうすることの中で、自分の五感が刺激されて、自分の身体が社会に開かれて、自分が新しくなっていく感覚を得ることができる、…この社会の中で生きているという強い実感を得ることができる。(牧野 2014:11)
このような仕事観は2000年代初頭から継続的にみられるものである。というのもこの仕事観は、「都会から離れて、田畑を耕し、地域の人々と親交を深めながら生きる」といったようないわゆる「田舎暮らし」志向と親和性の高いものであり、「田舎暮らし」関連の書籍自体は1995年頃から刊行数を急激に伸ばした後、2000年代に入ってからもコンスタントに刊行されているためである(立川 2005)。
一方で、2010年頃を境に2つの変化が存在する。第一の変化は、2000年代の『農業経営本』においてはスローな働き方の意義について言及されることは少ないのに対して、2010年代においてはスローな働き方が生むメリットが多く語られるというものである。第二の変化は、2000年代の『農業経営本』において「スローな働き方を重んじる仕事観」は単独で語られていたのに対し、2010年代においては「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」との共存が多くみられる点である。
この変化は、2000年代に「スローな働き方を重んじる仕事観」が語られていた『農業経営本』はいわゆる「田舎暮らし」本であったのに対し、2010年代におけるそれは単なる「田舎暮らし」本ではなくなったと言い換えることもできる。その証左に、2000年代には以下のようにみられた
【夢・ロマン】に対する言及が、2010年代にはみられなくなっている。
夢の晴耕雨読の生活の実現(斎藤 2000:46)
田舎を持たない山崎さんにとって、田舎で暮らすことは夢だった
(田舎暮らし研究会 2002 事例⑦:130)
「田舎暮らし」が夢やロマンとして語られていた時代において、スローな働き方は、その意義を問う必要もない自明なものであった。しかし2010年代においては、スローな働き方は様々な形で意味づけられるようになったのである。
第6節 他者の充足を重んじる仕事観
本節では、ボランティアや社会運動といった「職業ではない『仕事』」を通して実現される「他者の充足を重んじる仕事観」について分析を行う。この仕事観をあらわす典型的な言説には以下のようなものがあげられる。
僕はプロの農家ではないから、生産物で人の心を満たすことはできないが、農作業の面白さを伝えたり、食べることを通して多くの人が交流する場を設けたりすることで、役に立てることがあるのではないかと思っている。(永島 2012:187)
草援いボランティアの出発点は、利害関係ではありません。伝統を、風景を、田んぼを守りたいという気持ちが根幹です。(浅見 2012:313)
この仕事観がみられる『農業経営本』は非常に数少ない。上に挙げた浪見(2012)の本編においては「有機農業とは、農薬や化学肥料を使わずに安全で質のよい農作物を育てることにとどまるものではありません。行き過ぎた市場経済によって失われた人間と自然との関係、人間と人間との関係を、農業を通じて取り戻す運動です。(中略)私が実践する有機農業は、常にこうした社会運動の意味合いを含んでいます。」(浅見 2012:237)という記述が見られ、有機農業と社会運動の結びつきを確認することができる。しかし、やはり自由度や多様性が拡大した現代においては社会運動は成立しにくくなるのであろうか。
第7節 社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観
本節では、「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」について分析を行う。社会をより良いものにしたいという使命感と、その使命を仕事として成り立たせたいという思いの両方を併せもつこの仕事観をあらわす典型的な言説には、以下のようなものがあげられる。
現在の日本農業は、このようなひどいシステムの中で、輸入農産物という「黒船」に直面しているのである。(中略)しかし手をこまねいているわけにはいかない。少なくとも私は、こうした状況を黙っての見過ごすほどのお人好しではない。ただ文句を言って自己満足できる性格でもない。だから私は、現在の農協に代わる生産者組織(株)信州がんこ村を設立したのである。(横森 2002:239)
農村には資源すなわち「宝」はありますが、その「宝」を生かす担い手がまったく足りません。ですから、これからは都市と農村が連携して動けるようなビジネスモデルが必要となります。(曽根原 2011:218)
ここでいう「社会をより良くしたいという使命感」とは、概ね【耕作放棄地問題】【後継者問題(産地を守る)】【食料自給率問題】を解決しなければいけないという使命感である。
この仕事観をもつ著者にとって、この使命感が目的であり、ビジネスは手段に位置づけられる。「農」がビジネスとして成立し、「農」に関心を持つ人が増えることがこれらの問題解決に結びつくというロジックが大勢を占める。これは「経済的な豊かさを追求する仕事観」の持ち主がビジネスを目的に、こうした農業問題を手段に位置づけることとは対照的である。
また、この仕事観の持ち主は【物質主義への忌避感】を示すことが多い。
売り上げを上げるとはどういうことか?サラリーマンをされていた方ならおわかりかと思うが、市場の大きさが決まっているのだから、競争相手を蹴落とすか、新しい需要を発掘するかのどっちかしかない。(中略)けれども、実際にやってみると、新しい需要を発掘するというのは、すでに満足している人に満足は幻想だと思わせる仕事なのだ。(杉山 2005:6)
東京の大学に進学して、卒業後は10年間、銀行員をやっていたため、農業とは対極にある世界に生きていました。完全な都会型ビジネスの中にいて、生き物を育むどころか、お金がお金を生み出す輪の中にいたのです。それが社会の一面だということは理解していながらも、自分自身が一生続けていこうとは思いませんでした。僕の生き方とは違うと思っただけです。(鈴木 2010)
彼らは物質主義に対して忌避感を示しながらも、「農」の復興という使命感のためならば経済合理的な考えを持ち込むことを厭わないという、ある種アンビバレントな性質をもっている。この点において、この仕事観は前節で述べた仕事観とは似ているようで大きく異なっていることがわかる。
この仕事観は、2010年代の『農業経営本』においては支配的である。これらの『農業経営本』が「経済的リターン」を「社会的リターン」に従属させる形で語る以上、彼らが実際にどこまで「経済的リターン」の価値を重んじているのかは、残念ながら読み取ることはできない。しかし、「農」を通して「経済的リターン」と「社会的リターン」の両方が得られるという語りが2010年以降大きな支持を集めているということは事実であろう。
本章では、先行研究をもとにした7種類の仕事観から、「農業経営本」を分析を行った。7種類の仕事観のうち、「余暇に対する手段としての仕事観」およびボランティアや社会運動にみられる「他者の充足を重んじる仕事観」はほとんど確認することができなかった。また「自己実現を重んじる仕事観」は、「農業経営本」の本編においては頻繁にみられるものの、「はじめに」や「おわりに」で言及されるような中心的な仕事観ではなかった。
「経済的な豊かさを追求する仕事観」は、2008年から2010年頃に集中的にみられた。これは日本の深刻な不況と関連があると考えられるが、「農業経営本」の歴史の中では例外的な存在と言えるだろう。
2000年から2014年の15年にかけて、多数確認されたのは「スローな働き方を重んじる仕事観」、「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」、「やりたいことを重んじる仕事観」の3種類の仕事観であった。
「スローな働き方を重んじる仕事観」は2000年代前半からコンスタントに確認され、2010年頃からは「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」との共存が多くみられるようになった。
「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」は2010年代に入って急増し、現在の「農業経営本」においては「スローな働き方を重んじる仕事観」に代わって最も多くみられる仕事観となった。
「やりたいことを重んじる仕事観」は2000年代後半から多くみられるようになり、「経済的な豊かさを追求する仕事観」や「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」と共存することが多いほか、その両者よりも後ろの位置で語られることが多いという特徴をもっていた。
それでは、これらの結果が意味するところは何なのであろうか。次章ではその意味を考察する。
第4章 考察
本章では、前章の分析結果をふまえ、「農」ブームにおける仕事観と、「農」ブームから読みとくことのできる現代日本人の仕事観についてそれぞれ考察を加える。
第1節 「農」ブームにおける仕事観
本節では、第3章で行った分析をふまえ、「農」ブームにおける仕事観について考察を行う。
前章の分析からは、「農業経営本」にみられる仕事観にはトレンドがあることが明らかになった。大まかに言えば、2000年以降コンスタントにみられる「スローな働き方を重んじる仕事観」、2000年代後半より増加した「やりたいことを重んじる仕事観」、2008年から2010年に集中した「経済的な豊かさを追求する仕事観」そして2010年代に入り隆盛した「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」という流れである。
ここで今一度指摘しておきたいのは、こうしたトレンドは読者の需要をある程度反映したものであるということである。今回分析対象としている「農業経営本」の執筆者の多くはブームの到来以前から就農しているいわば新規参入のパイオニアである。したがって、それぞれの「農業経営本」が刊行されたタイミングには意味があると考えるのは当然であり、「農業経営本」における仕事観のトレンドが「読者受けの良さ」を考慮に入れたものでだと考えることは妥当であろう。
それでは考察に移ろう。まずは、2000年から2000年代後半にかけて「スローな働き方を重視する仕事観」が中心を占める時期である。この頃の「農」は、物質主義の対極に位置づけられるものとしてほぼ無条件に肯定的な価値を付与されている。よって農的な生き方には「夢」や「ロマン」が語られ、「スローな働き方を重視する語り」はあっても「なぜスローな働き方が重要なのか」が語られることは少なかった。
そして、この頃の「スローな働き方」はどちらかと言えば自分志向で語られるものであり、積極的に地域や「農」の在り方を変革していこうというものではない。この意味ではこの時期の「スローな働き方を重視する仕事観」は、ディスカバー・ジャパンの頃の農村に対する憧れ、立川の言う「農村空間の商品化」の延長線にあると言えるだろう。
1990年代以降「農」への参入障壁が緩和されていくなかで「農」と仕事を結びつき、グリーンツーリズムのような一時的な消費ではなく「田舎暮らし」という形において農村空間の消費が行われていたのである。
2008年から2010年にかけては、「経済的な豊かさを追求する仕事観」が増勢する時期が訪れる。この仕事観が確認されるのはほぼこの3年間に限られており、この3年間以外は「脱物質主義」的な仕事観が支配的である。高度経済成長期以来物質主義や合理主義の対抗軸として肯定的な価値を付与されてきた「農」であるから、「農」と「脱物質主義」のな仕事観が結びつくことに取り立てて目新しさはないだろう。しかし、リーマンショックのような不況期においては、その「農」ですら物質主義的な仕事観と結びつくという点には見るべきものがある。「この国が資本主義国家である以上『俺は仕事をした』というのは、ズバリ成果を数値的に出したときにいうことである。」(長田 2008:99)というような言説が「農」をテーマにした書籍に見られるということからは、「脱物質主義」が物質的にある程度満たされた環境から生まれるということを再確認させられる。
「経済的な豊かさを重んじる仕事観」が語られる『農業経営本』の本編には、「自己実現を重んじる仕事観」が語られるケースが多い。そしてこの時期は、「やりたいことを重んじる仕事観」が出現する時期でもある。前章でも述べた通り、この仕事観はこの時期「経済的な豊かさを追求する仕事観」との共存、それも“後出し”が多いのであった。
それでは、これらの組み合わせの意味することは何か。それは、「稼ぎばかりを強調することへの後ろめたさではないだろうか。「クリエイティビティの発揮が結果につながる」「仕事が趣味になる」といった語りを伴にすることで、「農業はこうすれば儲かる」という主張の無骨さは幾分緩和される。そのような意識が“後出し”には働いているのではないだろうか。
2010年代に入ると、「経済的な豊かさを追求する仕事観」は見られなくなり、「スローな働き方を重視する仕事観」が見られる『農業経営本』も、単なる「田舎暮らし」本ではなくなっていく。この時期は、「スローな働き方を重視する仕事観」「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」「やりたいことを重んじる仕事観」という3種類の仕事観が、短い「はじめに」と「おわりに」の中に入り混じるようになる時期なのである。
2000年代には「夢」や「ロマン」としてほぼ無条件に肯定されていた「スローな働き方」は、他者とのつながりを感じられる場、「ありがとう」の声をかけてもらえる仕事、農作業を通して自らのアイデンティティを回復する場など、様々な形で意味づけられるようになる。また「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」と結びつく場合には、どちらかと言えば自分志向だった「スローな働き方」は、「他者(社会)のために」という性質も帯びてくるのである。
そして、2012年に増加した「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」は、2013年にはその数を減らすものの(2013年は『農業経営本』の刊行数も少ない)、2014年には急増する。前節でも述べたように、この仕事観をもつ著者の多くは経済的リターンを社会的リターンに従属させ、【物質主義への忌避感】を示す。すなわち、「農」の復興のような社会的使命を達成するための手段として、ビジネスとして成り立つ、稼げる農業の実現を目指すのである。
彼らが実際にどの程度「稼ぎたい」という思いをもっているかは定かではない。「農業経営本」の執筆者として成功を収めている著者たちは、純粋に使命感のみに燃えている人たちのようにも思われる。しかし、この仕事観が近年急速に読者の支持を集めている背景には、「いいとこどり」の精神がある可能性が考えられる。
経済的なリターンばかりを追い求めるのも無粋に感じられる。「農」は食と関わる身近なテーマだし、日本の「農」の現状には不安もあるけれど、かといって社会運動やボランティアを通して純粋に社会的リターンを追い求めるような思い切りも難しい。そのような人々にとって、その両者の「いいとこどり」ができるようなこの働き方は、大変魅力的に映るのではないだろうか。
最後に忘れてはならないのは、「『やりたいこと』を重んじる仕事観」は2010年代に入ってなお、大きな影響力をもっているという点である。
以下に一例を示そう。
「なんで西辻さんは農業にこだわるんですか?」と聞かれることが多くなった。その時に答える言葉は「農業が好きだから」なんだが、なぜ好きなのかをもっと突き詰められるといつももやけてしまう(西辻2012:4)
本書の執筆を通して、僕がどうして農業が好きなのかが自分自身わかりました。それは「自分のことが好きでその自分を作ってくれた福井、日本、地球と広がってさらにそのエリアごとの人間関係、そして最後に全てをつなぐ土」に感謝をしていて恩返しをしたいという思いです。(西辻2012:268)
この仕事観においては仕事を好きだと思えること、仕事を楽しいと思えることが重要とされる。「経済的な豊かさを追求する仕事観」が支配的であった00年代終盤においては、「好き」や「楽しい」の原動力は「自己実現」であった。しかし一方で、「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」が支配的な2010年代においては、この例のように「他者(社会)のため」が「好き」や「楽しい」と結び付けられるのである。
第2節 「農」ブームから読みとく現代日本人の仕事観
前節では、「農」ブームにおける仕事観について考察を行った。本節では前節での考察をふまえて、現代日本人の仕事観に関して、「農」ブームの分析から得られる示唆について述べることとしたい。
先行研究において、働くことの自明性が失われた1990年代以降には新たな働く意味が求められるようになることが指摘されていた。では、本研究が分析対象とした2000年から15年間の「農」の領域でも、同じことが起こっていただろうか。
確かにこの15年間、『農業経営本』においては様々な形で仕事が意味づけられてきた。意味づけの中心となったのは「スローな働き方を重んじる仕事観」「やりたいことを重んじる仕事観」「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」であり、これらは「手段としての仕事観」と区別する意味でも、仕事を“積極的に”意味づけようとする試みであったと言えよう。
そして、仕事を積極的に意味づけようとする流れは、この15年間にも加速していったように思われる。2000年代の途中まではほとんど「スローな働き方」の実現の場としか期待されていなかった「農」は、今では「はじめに」「おわりに」の短い紙幅のなかにたくさんの仕事観が書き綴られているのを見ることができる。
もちろんこの変化は日本人の仕事観の変化だけによるものではなく、「農」という領域そのものの変化が寄与していることは間違いない。農家のあとつぎでない人間が「農」の世界に足を踏み入れることが現実的に可能になったのは僅か25年ほど前のことであり、始めは「田舎暮らし」を楽しむだけのつもりだけだった“お客さん”も、時とともに農村のなかで主体性を獲得し、仕事を通して色々なことを試みたくなるはずである。しかし、『農業経営本』における仕事観の変化がそれぞれのタイミングで起こったことには、確実に「農」自体の変化だけでは説明できない意味があるだろう。
一方で、『農業経営本』のなかには、仕事を積極的に意味づけようとする流れとは真逆の流れが存在する。それは「意味づけへの疲れ」とも読める現象であり、あれこれと意味づけをする必要のない「本質」や「本能」に働く自明性を求めるものである。少し例をみてみよう。
人間のDNAの中には、命を育むことに喜びを見出す「本能」が組み込まれているからではないかと思います。(鈴木2010:63)
やはり日本人には農耕民族としてのDNAがあるのだろうか。僕は農作業をしていると、肉体も心も喜んでいるのがわかる。眠っていたような能力が呼び覚まされるような感覚。ダイレクトに響いてくる、生きているという実感(永島2012:158)
「ただ畑に出て作業する」という極めてシンプルな中に、私たちが生きるのに必要なすべて(意欲や希望や心の充足)の要素がつまっている(小島2014:163)
ここで、第1章第1節で触れた「労働からの解放」論者の論を振り返ってみよう。人は全体的で自律的な職人仕事には喜びを感じることができる。あるいは、本当の意味で生活に必要なものを生み出す労働は本質的な労働であると言える。しかし、それら以外の労働は、近代以降肯定的な価値を付与されてきに過ぎない、そのような労働に意味を求めることには人は縛られすぎている……。彼らの主張は、やや強引にまとめればこのようなものであった。
この「労働からの解放」論者の後半部分の主張の是非をここで検討することはしないが、「しかし」以前の主張は妥当と言えるのではないだろうか。そして、上に示したような言説はそこに働く意味を感じているものである。
勿論これらの著者は、「社会的リターンと経済的リターンの両方を追求する仕事観」等の仕事観を記している。すなわち、彼らは一方では現代的な方法で仕事を積極的な意味づけを行いながらも、もう一方では本質的なものに働く意味を求めている。この現象からは、仕事に対して積極的に意味づけを行うことが規範的である現代において、「意味づけへの疲れ」「意味づけの限界」のようなものが生じる可能性を指摘することができるのではないだろうか。そしてこの点こそが、「農」ブームに着目する面白さであるように思われるのである。
終章 働く意味の希求がもたらすもの
本論考が明らかにしたことは、15年間の「農業経営本」において、「農」という仕事には様々な意味づけが行われてきたこと、意味づけは増加してきたこと、一部には「意味づけへの疲れ」が垣間見えることでもある。
そして、その背後に見え隠れするのはやはり、仕事に意味を求めることの規範化である。仕事を単なるお金を稼ぐための手段であるかのように語ることは、今の日本においては受け入れられにくい。「農業経営本」の執筆者たちの間に「自分たちの仕事がいかに意味のある仕事なのかを知ってもらいたい」という意識はおそらくあるだろうし、仕事の意味を強調する彼らの語りにこの規範は影響を及ぼしているだろう。
それでも彼らは成功者である。自分たちの仕事の意味をしっかりと実感できている彼らは、規範の影響を受けることはあっても規範に苦しむことはない。現在の仕事の意味は大いに語っても、以前の仕事をネガティブに語ることは少ない。補助要素群にもあった【サラリーマンに向いていない】【都会の生活に向いていない】といった消極的な語りはここ数年の「農業経営本」においてはほとんど見られないのである。
しかし、読者たちはどうであろうか。序章でも述べたように、仕事の意味は誰もが容易に感じられるものではない。読者のなかには、仕事に意味は求めるべきという規範のもとで自身の生き方に不安を覚え、「農業経営本」に手をのばす人も多いだろう。そして読後には規範を再確認するだろう。もしもこの規範が存在しなければ、このような類の不安を抱える人は今よりは少ないのではないだろうか。
このように、21世紀の「農」ブームは、規範のもとで仕事の意味を希求する人々によって成り立っていると考えられるのである。さらに言えば、この「農」ブームは決して仕事観だけの問題ではない。本研究では触れることはなかったが、仕事に意味を求めることの規範化は、「農」そのものの問題ともなりうる。
「農」の現実は厳しく、経営がうまくいっていない新規就農者の割合は近年増加しており、新規就農者の約3割が5年以内に離農してしまっていると言われている。もしも「農」ブームにのって「農」の世界に足を踏み入れた人の一部がこのような現実をつくっているのだとすれば、「農」ブームの在り方自体を再考する必要がある。
また、「農」という仕事の本質的な性格を拠り所とし、「農」の誇りを取り戻そうとする傾きには慎重にならなければならない。資本主義のなかで農業と農民が主に役である社会を建設することは20世紀の農業の一つの夢であったが(藤原 2007)、そうした農本主義的な思想が過去に犯した過ちを我々は忘れてはならない。
したがって、本研究で行った「農業経営本」の分析が示唆する仕事に意味を求めることの規範化は、それに翻弄される人々の問題でもあり、「農」そのものの問題でもあると言える。確かに働くことに意味はないとする「労働の解放」論は極論かもしれない。しかし、働くことに意味はないと割り切る考え方に対しても寛容な社会でなければ、仕事に意味を見出せない人々は逃げ場を失い、絶えることのない働く意味の希求に苦しむことになるだろう。
文献一覧
秋津元輝,2007,「カルチュラル・ターンする田舎――今どき農村社会研究ガイド」,野田公夫編,『生物資源問題と世界』,147-177,京都大学学術出版会.
秋山慶治,2004,「誰のための労働か」,学文社.
Arendt, Hannah., 1958, The Human Condition, Univ of Chicago Pr
(=2015,森一郎訳,「活動的生」,みすず書房).
安藤喜久雄,1996,「企業に働く人々:個と共同性」,桜井洋・北澤裕・誘里茂編『ライフスタイルと社会構造』,日本評論社.
Dumazedier, Joffre., 1972, Vers une civilization du loisir?, Julliard
(=1972,中島嶺訳,「余暇文明へ向かって」,東京創元社).
藤村正之,1995,「overview:仕事と遊びの社会学」,井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉見俊哉編『仕事と遊びの社会学』,岩波書店.
藤原辰史,1997,「二〇世紀農学のみた夢と悪夢―ナチスは農業をどう語ったのか?」,野田公夫編,『生物資源問題と世界』,179-201,京都大学学術出版会.
Gorz, Andr’e., 1988, Métamorphoses du travail Qu’ete du sens: Critique de la rasion économique
(=1997,真下俊樹訳,「労働のメタモルフォーゼ」,緑風出版).
橋口昌治,2014,「揺らぐ企業社会における『あきらめ』と抵抗――『若者の労働運動』の事例研究」,Vol.65 (2014) No.2, pp.164-178.
Habermas, Jürgen., 1981, Theorie des kommunikativen Handelns, Band2, Suhrkramp
(=1987,丸山高司ほか訳,『コミュニケーション的行為の理論(下)』, 未来社).
久木元真吾,2003,「『やりたいこと』という論理・フリーターの語りとその意図せざる帰結」,『ソシオロジ』,第48巻第2号,78-89.
平川俊,1995,「会社文化のうちとそと」,井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉見俊哉編『仕事と遊びの社会学』,岩波書店.
引用澄夫,1986,「農家労働力の統計分析」,農林統計協会.
本田由紀・筒井美紀編,2009,『リーディングス 日本の教育と社会 第19巻・仕事と若者』,日本図書センター.
一宮真佐子,2008,「ポピュラーカルチャーにおける農業・農村表象とその変化―現代マンガを対象として―」,村落社会研究ジャーナル,Vol.15, No.1, 13-24.
井上俊,1995,「生活の中の遊び」,井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉見俊哉編『仕事と遊びの社会学』,岩波書店.
今村仁司,1998,『近代の労働観』,岩波書店.
石田光男,1990,「賃金の社会科学」,中央経済社.
石井清輝,2007,「『消費される〈農村〉』の誕生―戦後日本のナショナリズムとノスタルジア―」,哲学,117, 125-156.
金子郁容・田中清隆,2009,「ソーシャルファイナンスに見る,これからの『働き方』―育てつつ事業を行う可能性―」,橋本俊昭・編『働くことの意味』,ミネルヴァ書房.
桑木咲子,2013,「ディスカバー・ジャパンをめぐって:耕作する意思から生まれる多面性」,日本学報,32, 131-145.
経済企画庁国民生活局編,1991,「『個人生活優先社会をめざして』第13次国民生活審議会総合生活部基本政策委員会中間報告」,大蔵省印刷局.
牧野智和,2015,「日常に進入する自己啓発・生き方・手帳術・片づけ」,勤草書房.
前田信彦,2010,「仕事と生活」,ミネルヴァ書房.
Meda, Dominique., 1998, Le Travail: Une valeur en voie de disparition, Aubier.
(=2000,若森章孝・若森文子訳,『労働社会の終焉――経済学に挑む政治哲学』,法政大学出版局).
間々田孝夫,2005,「消費社会のゆくえ――記号消費と脱物質主義」,有斐閣.
見田宗介,1978,「近代日本の心情の歴史――流行歌の社会心理史」,講談社.
杜新,2001,「『日本人の労働観』研究の歴史的変遷――その位相と今日的課題」,慶應義塾大学社会学研究科紀要第52号,39-49.
中安定子,1995,「労働力流出と農業構造(中安定子論文集4)」,農林統計協会.
日本村落研究学会,2005,「消費される農村・ポスト生産主義下の『新たな農業問題』」.
農林水産省,2015,「平成27年度版 食料・農業・農村白書」,日経印刷株式会社.
野田公夫,2007,「現代農業革命と日本・アジア人・土地(自然)関係の再構築にむけて」,野田公夫編,『生物資源問題と世界』,207-232,京都大学学術出版会.
小熊英二,2012,「社会を変えるには」,講談社現代新書.
Ritzer, George., 2004, Globalization of Nothing, Pine Forge Press
(=2005,山本徹夫・山本光子訳,『無のグローバル化――拡大する消費社会と「存在」の消失』,明石書店).
Robertson, Jennifer., 1995, Hegemonic Nostalgia, Tourism, and Nation-Making in Japan, Senri Ethnological Studies, 38.
Rosso, B. D., Dekas, K.H. and Wrzesniewski, A., 2010, On the Meaning of Work; A Theoretical Integration and Review.
Research in Organization Behavior, Vol.30:91-127.
杉村芳美,2009,「人間にとって労働とは――『働くことは生きること』」,橋本俊昭・編『働くことの意味』,ミネルヴァ書房.
杉村芳美,2013,「成熟社会で〈働く〉こと」,猪木武徳・編『〈働く〉は、これから』,岩波書店.
橋本俊昭,2009,「働くということ――偉人はどう考えたか」,橋本俊昭・編『働くことの意味』,ミネルヴァ書房.
高橋誠・中川秀一,2002-2003,「人々のもつ『農村像』の特徴」,農村計画学会誌,Vol.21, No.2, 143-152.
田代洋一,1976,「農家労働力流動化の現段階的性格」,田代隆・花田仁伍編『現代日本資本主義における農業問題』,お茶の水書房.
立川雅司,2005,「ポスト生産主義への移行と農村に対する『まなざし』の変容」,年報村落社会研究第41集,農山漁村文化協会.
塚本学,1991,「都会と田舎―日本文化外史」,平凡社.
寺崎正啓,2009-2010,「現代若者の労働観―フリーターをめぐる“やりたいこと”と労働の”脱魔術化・際魔術化“」,ソシオロジ,Vol.54, No.2, 55-70.
徳野貞雄,1988,「農業問題の今日的意味」,社会学評論,38, 410-420.
宇野重規,2013,「〈地域〉において〈働く〉こと」,猪木武徳・編『〈働く〉は、これから』,岩波書店.
渡辺伸一,1991,「脱物質主義的価値と新しい社会運動」,年報社会学論.
全国農業会議所・全国新規就農相談センター, 2002, 「新規就農者の就農実態に関する調査結果 – 平成13年度 -」,
全国農業会議所・全国新規就農相談センター, 2007, 「新規就農者の就農実態に関する調査結果 – 平成18年度 -」,
全国農業会議所・全国新規就農相談センター, 2011, 「新規就農者の就農実態に関する調査結果 – 平成22年度 -」,
全国農業会議所・全国新規就農相談センター, 2014, 「新規就農者の就農実態に関する調査結果 – 平成25年度 -」,
「農業経営本」一覧(年次順)
- 吉津耕一, 2000, 『定年になったら農業をやろう – 大地と空といい汗と』, オーエス出版.
- 役重真喜子, 2000, 『ヨメより先に牛がきた – はみだしキャリア奮戦記』, 家の光協会.
- 田舎暮らしネットワーク編, 2000, 『田舎暮らし大募集』, 田舎暮らしネットワーク.
- 伊藤伝一, 2000, 『片手にクワを – 子や孫に手渡そう安全な食糧』, せせらぎ出版.
- 諏訪恭也, 2000, 『定年夫婦田園ライフの愉しみ』, 中央公論新社.
- 齋藤一夫, 2000, 『農業をやろう!―田舎で生きる人のための「就農マニュアル」がんばれ!ニューファーマー』, 山海堂.
- 玉村豊男, 2000, 『小さな農園主の日記』, 講談社現代新書.
- ダイソー実用ハンドブック14, 2000, 『いなか暮らしの本―成功の秘訣はこれ!実例満載』, 大創産業.
- “農”ある暮らしを実践する会, 2000, 『定年農業のススメ―元気に、欲張らず、楽しく生活できる』, 中経出版.
- 熊谷嘉尚, 2001, 『山暮しで人生を変えてみた』, 講談社.
- 現代農業増刊, 2001, 『ナチュラルライフ提案カタログ―手づくりの道具 手づくりの教室 手づくりの逸品』, 農山漁村文化協会.
- 有野民雄, 2002, 『農業に転職する―失敗しない体験的「実践マニュアル」』, プレジデント社.
- 宮崎猛, 2002, 『アグライフのすすめ』, 家の光協会.
- 日渉義雄, 2002, 『森暮らしの家全スタイル:ホーム・エコロジストの田園生活』, 小学館.
- 新田穂高・城ノ内まつ子, 2002, 『自然の暮らしがわかる本―自然に生きる田舎に暮らす自給自足の知恵と暮らし方』, 山と渓谷社.
- 田舎暮らし研究会編, 2002, 『田舎暮らしバンザイ!!』, 学習研究社.
- 横森正樹, 2002, 『夢の百姓―「正しい野菜づくり」で大儲けした男』, 白日社.
- 舘澤貢次, 2002, 『いま、アグリ・ビジネスがおもしろい!―工場化・バイオ・安全をキーワードに、「農」に挑む先端企業』, オーエス出版.
- 長沢正教, 2002, 『山里に生きる』, 郁朋社.
- 現代農業増刊, 2002, 『青年帰農―若者たちの新しい生き方』, 農山漁村文化協会.
- 全国農業新聞いきいきアグリウーマン取材班編, 2003, 『もうひとつの農おこし―いま女性起業が元気!』, 全国農業会議所.
- 塩見直紀, 2003, 『半農半Xという生き方』, ソニー・マガジンズ.
- 北島淳朗・北島ゆきみ, 2003, 『廃校に暮らす―森の中のスローライフ』, 南方新社.
- 小川光, 2004, 『畑のある暮らし方入門―土にふれ、癒される生活』, 講談社+α新書.
- 斎藤一夫・大日招平, 2004, 『田舎暮らしをさっさとやろう』, 自由国民社.
- 田中淳夫, 2004, 『田舎で起業!』, 平凡社新書.
- 大森泰介, 2004, 『誰も教えてくれない「農業」商売の始め方・儲け方―農業を面白くする秘訣は「儲けのしくみ」を作ることだ!』, ぱる出版.
- 今関知良, 2004, 『虫嫌いの田舎暮らし』, 家の光協会.
- 構島弘文, 2004, 『会社を辞めて田舎へgo!』, 飛鳥新社.
- 大森昌也, 2005, 『自給自足の山里から―家族みんなで親文百姓』, 北斗出版.
- 全国新規就農相談センター編, 2005, 『新・農業人列伝―新規参入事例集 第3集』, 全国農業会議所.
- 豊田菜穂子, 2005, 『ロシアに学ぶ週末術―ダーチャのある暮らし』, WAVE出版.
- 今関知良, 2005, 『今関さんちの自給自足的生活入門』, 家の光協会.
- 野沢一馬, 2005, 『儲かる「農業」ビジネスの始め方―好きな農業を会社にするには「儲けのサイクル」が必要だ!』, ぱる出版.
- 杉山経昌, 2005, 『農で起業する!―脱サラ農業のススメ』, 筑地書館.
- 岡村健, 2005, 『旅のつづきは田舎暮らし―僕とカミさんの定年後・南会津記』, 風土社.
- 全国新規就農相談センター 編, 2006, 『新・農業人列伝―新規参入事例集 第4集』, 全国農業会議所.
- 坂口和彦, 2006, 『農業をやろうよ』, 東洋出版.
- 神出安雄, 2006, 『あなたにもできる農業起業のしくみ』, 日本実業出版社.
- 堀江康敬, 2006, 『団塊世代の田舎暮らし―黄金リタイア』, インデックス・コミュニケーションズ.
- 杉山経昌, 2006, 『農!黄金のスモールビジネス』, 筑地書館.
- 塩見直紀, 2006, 『半農半Xという生き方 実践編』, ソニー・マガジンズ.
- 田中淳夫, 2006, 『田舎で暮らす!』, 平凡社新書.
- 相川良彦・會田陽久・秋津ミチ子・本城昇, 2006, 『農村をめざす人々―ライフスタイルの転換と田舎暮らし』, 筑波書房.
- 大森泰介, 2006, 『田舎で見つけるゆったり農楽ぐらし―「農業起業」の始め方・稼ぎ方・楽しみ方』, ぱる出版.
- 新田穂高, 2006, 『家族で楽しむ自給自足』, 文化出版局.
- 全国新規就農相談センター監修, 2006, 『新規就農ガイドブック―始めよう!農業』, 全国農業会議所.
- 斎藤一夫・大日招平, 2006, 『田舎暮らしをさっさとやろう+α』, 自由国民社.
- 樋島弘文, 2006, 『馬頭のカバちゃん―田舎暮らし奮闘記』, 日経BP社.
- 全国農業会議所・都道府県農業会議編, 2006, 『担い手になろう!-25のポイント』, 全国農業会議所.
- 現代農業増刊, 2007, 『脱・格差社会―私たちの農的生き方』, 農山漁村文化協会.
- 塩見直紀, 2007, 『綾部発半農半Xな人生の歩き方88―自分探しの時代を生きるためのメッセージ』, 遊タイム出版.
- 高森直史, 2007, 『気ままに大自然“アウトドア生活”のすすめ!』, 光人社.
- 佐藤彰啓, 2007, 『リタイア後は田舎で暮らそう』, 講談社.
- 塩見直紀と種まき大作戦編著, 2007, 『半農半Xの種を播く―やりたい仕事も、農ある暮らしも』, コモンズ.
- 高品徹治, 2007, 『月10万円で豊かに生きる田舎暮らし』, 幻冬舎文庫.
- 玉村豊男, 2007, 『田舎暮らしができる人できない人』, 集英社新書.
- 清水たくや, 2007, 『田舎でスローライフを極める』, 学芸出版社.
- 中島正, 2007, 『農家が教える自給農業のはじめ方―自然卵・イネ・ムギ・野菜・果樹・農産加工』, 農山漁村文化協会.
- 全国新規就農相談センター編, 2008, 『新・農業人列伝―新規参入事例集第5集』, 全国農業会議所.
- 今関知良, 2008, 『ほほどほどに食っていける田舎暮らし術』, 創森社.
- 堀口博行, 2008, 『週2日だけ働いて農業で1000万円稼ぐ法』, ダイヤモンド社.
- 齋藤訓之, 2008, 『農業成功マニュアル―「農家になる!」夢を現実に』, 翔泳社.
- 塩見直紀, 2008, 『半農半Xという生き方』, ソニー・マガジンズ新書.
- 大桃美代子, 2008, 『ちょっと農業してきます』, 成美堂出版.
- 大森森介,2008,『誰も教えてくれない「農業」商売の始め方・儲け方―“頭”を使って儲ける!成功のポイントは“経営的視点”を持つこと!!』,ぱる出版.
- 長田竜太,2008,『米で起業する!―ベンチャー流・価値創造農業へ』,築地書館.
- 杉山経昌,2009,『農で起業!―新しい農業のススメ』,築地書館.
- 大内正伸,2009,『山で暮らす愉しみと基本の技術』,農山漁村文化協会.
- 週刊ダイヤモンド編,2009,『農業入門―「農」をシゴトにしよう!週末農業から高収益経営まで』,ダイヤモンド社.
- 筒吹文郎・白土陽子,2009,『百姓入門―舌ワズ汚サズ争ワズ』,新泉社.
- 大森森介,2009,『脱サラ就農は“事前準備”で9割成功する―農業を一生の友として生活していくための就農バイブル!』,ぱる出版.
- 遠藤ケイ,2009,『遠藤ケイの田舎暮らしは愉快だ!』,千早書房.
- 小西史明・渡辺啓巳,2009,『農業に就く!―農業に必要な技術・資金・土地のしくみ』,秀和システム.
- 嶋﨑秀樹,2009,『儲かる農業―「ど素人集団」の農業革命』,竹書房.
- 常瀬村泰,2009,『ゼロからでもできる農業のススメ』,扶桑社.
- 石川県担い手育成総合支援協議会,2009,『農林漁業で起業した女性たち』,石川県担い手育成総合支援協議会.
- 大森森介,2009,『「農業」でラクしてお金を稼ぐ方法―楽しく働く!頭を使って賢く稼ぐ!新・脱サラ農業成功バイブル!』,ぱる出版.
- 増山博康,2009,『半農生活をはじめよう―つくって・食べて・売ってできれば月10万円稼ぐ』,かんき出版.
- 郡ひとし,2009,『田舎ごこち〜ソウダ、田舎デ暮ランウ。』,ワン・ライン.
- 出山健示・木谷充,2009,『自然職のススメ』,二玄社.
- 小田公美子,2009,『週1から始める元気な農業』,朝日新聞出版.
- アグリ・ライターズ,2009,『本気で「農業」をやりなさい』,オークラ出版.
- 松下一郎,鈴木康央,2009,『夢で終わらせない農業起業―1000万円稼ぐ人、失敗して借金作る人』,徳間書店.
- 有坪民雄,2009,『農業で儲けたいならこうしなさい!』,ソフトバンククリエイティブ.
- 池田美佳・小豆佳代・木越弘美,2009,『農活:はじめる!my農業スタイル』,本の泉社.
- 西谷桂子,2009,『だから、田舎に暮らす』,牧歌舎.
- 後藤雅浩,2009,『農と都市近郊の田園暮らし』,毎日新聞社.
- 大矢賀政昭・河東仁・空閑厚樹・佐藤太編著,2009,『つながる喜び―農的暮らしとコミュニティ』,現代書館.
- 永峰英太郎,2009,『「農業」という生き方―ど素人からの就農入門』,アスキー新書.
- 全国新規就農相談センター監修,2009,『新規就農ガイドブック―始めよう!農業』,全国農業会議所.
- 川上康介,2009,『農民になりたい』,文春新書.
- 伊藤裕樹監修,2009,『新農民になろう!―就農計画の設計と実例』,技術評論社.
- 石坂晴海,2009,『お百姓のススメ―大地とともに豊かに暮らす「就農族4人」の生き方』,小学館.
- 齋藤訓之,2010,『農業をはじめたい人の本―作物別にはじめ方が全部わかる就農完全ガイド』,成美堂出版.
- 松木一浩,2010,『農はショーバイ!』,アールズ出版.
- 橋本哲弥,2010,『最新農業ビジネスがよ~くわかる本―新規就農・農業参入に役立つ情報満載』,秀和システム.
- 鈴村源太郎,2010,『農村ワーキングホリデー・ガイド―人と「農」とを結ぶありのままの農家体験』,家の光協会.
- 山下一仁,2010,『企業の知恵で農業革新に挑む!―農協・減反・農地形を解析して新ビジネス創造』,ダイヤモンド社.
- 天明伸浩・佐藤端三,2010,『転身!!リアル農家―等身大の新規就農』,新聞日報事業社.
- 潮野雄二郎,2010,『農業はじめてbook』,小学館集英社プロダクション.
- 澤浦彰治,2010,『小さく始めて農業で利益を出し続ける7つのルール―家族農業を安定経営に変えたベンチャー百姓に学ぶ』,ダイヤモンド社.
- 加藤大吾,2010,『地球に暮らそう―生態系の中に生きるという選択肢』,旅と冒険社.
- 農山漁村女性・生活活動支援協会編,2010,『ヒメ、農民になる―農業をしたい女性に贈る初めての就農ガイド』,農山漁村女性・生活活動支援協会.
- 神戸新聞総合出版センター編,2010,『ひょうごの田舎暮らし』,神戸新聞総合出版センター.
- 鈴木誠,2010,『脱サラ農業で年商110億円!―元銀行マンの挑戦』,角川書店.
- 木内博一,2010,『最強の農家のつくり方:「農業界の革命児」が語る究極の成長戦略』,PHP研究所.
- 大島七々三,2010,『農業を起業する~勝てるビジネスに変えた若者たちの方法』,アスペクト.
- 藤田和芳,2010,『有機農業で世界を変える-ダイコン一本からの「社会的企業」宣言』,工作舎.
- 田中進,2010,『ぼくらは農業で幸せに生きる』,ザ・ブック.
- 全国農業会議所,2011,『新規就農実現への道。-新規就農ナビゲーションブック』,全国農業会議所.
- 藤井勝彦,2011,『農業を仕事にする!-“夢で終わらせなかった人たちによる「就農」「転職」マニュアル”』,大和出版.
- 産学社編集部・川上清市編,2011,『市民農園ガイド-自然・食・人とふれあう 関東・近県版』,産学社.
- 曽根原久司,2011,『日本の田舎は宝の山-農村起業のすすめ』,日本経済新聞出版社.
- 木村彬・吉田修・青山浩子,2011,『新しい農業の風はモクモクからやって来る』,商業界.
- 斎藤融・斎藤周子,2011,『前略。農家、はじめました。』,ゴルフダイジェスト社.
- 中島恵理,2011,『田園サスティナブルライフ-八ヶ岳発!心身豊かな農ある暮らし』,学芸出版社.
- 中塚雅也,2011,『農村で学ぶはじめの一歩-農村入門ガイドブック』,昭和堂.
- 岡崎秀明,2011,『知識ゼロからの農業ビジネス入門』,幻冬舎.
- はたあきひろ,2011,『現役サラリーマンの自給自足大作戦-「菜園力」で』.
- 藤野直人,2011,『本気で稼ぐ!これからの農業ビジネス-農業所得1000万円を作りだす「中規模流通」という仕組み』,同文舘出版.
- 岩佐十良,2011,『田舎暮らしの方法』,明治書院.
- いいだかなこ,2011,『わたしがあぐりびとになるまで-ゼロからの手づくり就農物語』,野草社.
- 嶋﨑秀樹,2012,『儲かる農業-「ど素人集団」の農業革命』,竹書房新書.
- 曽根原久司,2012,『農村起業家になる-地域資源を宝に変える6つの鉄則』,日本経済新聞出版社.
- ブレインワークス・東北地域環境研究室 共著,2012,『東北発!女性起業家28のストーリー-女性ならではの知恵と工夫で農業ビジネスに新しい風を』,カナリア書房.
- 西辻一真,2012,『マイファーム荒地からの挑戦-農と人をつなぐビジネスで社会を変える』,学芸出版社.
- 菜穂子,2012,『山形ガールズ農場!=Yamagata Girls Farm-女子から始める農業改革』,角川書店.
- 曽根原久司・えがおつなげて編,2012,『田舎の宝を掘り起こせ-農村起業成功の10か条』,学芸出版社.
- 永島敏行,2012,『青空市場で会いましょう-日本の農と食はすばらしい』,家の光協会.
- 浅見彰宏,2012,『ぼくが百姓になった理由(わけ)-山村でめざす自給知足』,コモンズ.
- オノミユキ,2012,『山村大好き家族』,サンライズ出版.
- 豊田菜穂子,2013,『ダーチャですごす緑の週末-ロシアに学ぶ農の暮らし』,新評論.
- 古屋富雄,2013,『兼農サラリーマンの力-農業の新しい時代が始まる』,家の光出版.
- 深谷泰造,2013,『味なじいさん-げんきに楽しく楽農楽食』,鳥影社.
- 大内正伸,2013,『楽しい山里暮らし実践術』,学研パブリッシング.
- 大澤信一,2013,『プロフェッショナル農業人-”儲かる農業”をどうつくるか』,東洋経済新報社.
- オノミユキ,2013,『山村大好き家族』,サンライズ出版.
- 小島希世子,2014,『ホームレス農園-命をつなぐ「農」を作る!若き女性起業家の挑戦』,河出書房新社.
- 牧野篤,2014,『農的な生活がおもしろい-年収200万円で豊かに暮らす!』,さくら舎.
- 松尾靖子,2014,『ようこそ、ほのぼの農園へ-いのちが湧き出る自然農の畑』,地湧社.
- 藤井久子,2014,『農業者という生き方』,ぺりかん社.
- 塩見直紀,2014,『半農半Xという生き方』,筑摩書房.
- 林美香子,2014,『農業・農村で幸せになろうよ-農都共生に向けて』,晃洋出版.
- 小林和明,2014,『自給自足という生き方の極意-農と脳のほんとう』,ぷねうま舎.
- 古野隆雄,2014,『農業は脳業である-困ったときもチャンスです』,コモンズ.
- 蓮見よしあき,2014,『ゼロから始めて確実に夢を叶える農業起業-理想のライフスタイル始めませんか?』,みらいパブリッシング.
- 三好かやの・高倉なを・斉藤勝司,2014,『私、農家になりました-就農』.
- 金子勝・武本俊彦,2014,『儲かる農業論-エネルギー兼業農家のすすめ』,集英社新書.
- 芥川仁・阿部直美,2014,『里の時間』,岩波新書.
- 蓮見よしあき,2014,『SNSで農業革命-最小限の資金で強い農業を』,SGビジネス双書.
- 和田芳治,2014,『里山を食いものにしよう-原価0円の暮らし』,阪急コミュニケーションズ.
- 片山修,2014,『年商50億を稼ぐ村上農園の「脳業」革命』,潮出版社.
- 『いなか暮らしの本』編集部編,2014,『おひとりさまの田舎暮らし』,宝島社新書.
- 早川徹,2014,『田舎暮らしを夢見る人のマルチハビテーションライフ』,幻冬舎メディアコンサルティング.
- 嶋田成子,2014,『田舎暮らしは心の良薬-ネオン街40年から180度転換里山生活奮闘記 ストレス満タンは危ない!』,誠文堂新光社.
- 久松達央,2014,『小さくて強い農業をつくる-就職しないで生きるには21』,晶文社.
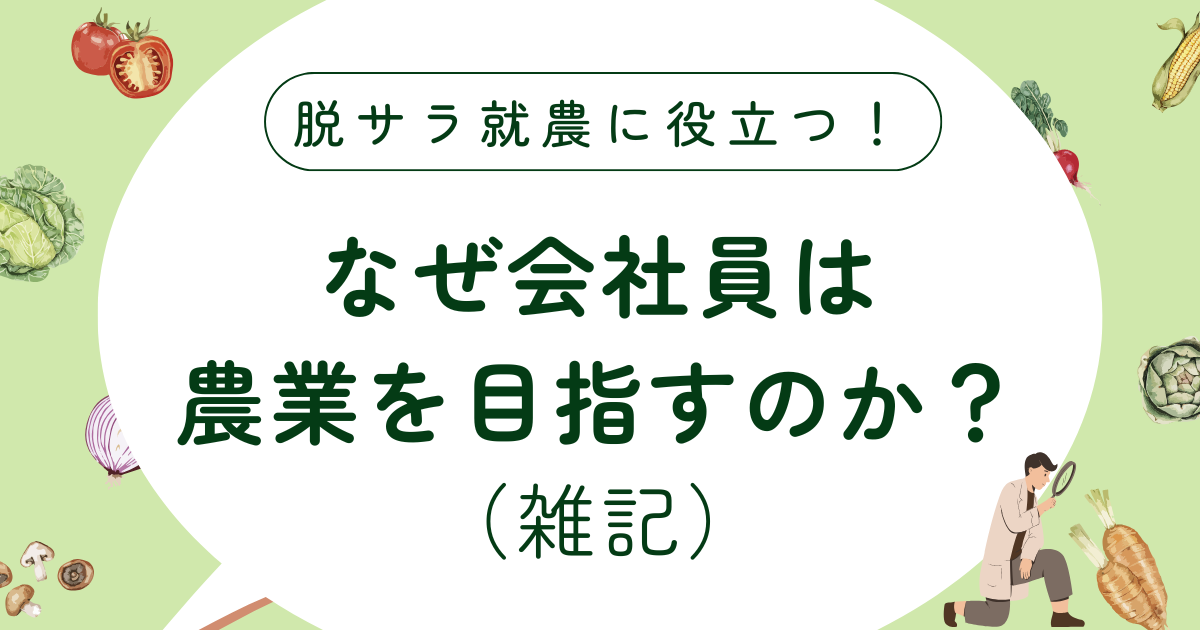

コメント