BT剤の定期散布やニンニクの植え付けなどを実施。
本日のトピックは、ついつい欲がでるが、追い播種(生育不良などで空いてしまった区画に後から種をまき、収量のリカバリを図ること)はやめておいた方がよいと思う、というお話です。
05:30-12:30 BT剤散布・追肥・中耕・除草・土寄せ
- キャベツ類、ブロッコリー類、大根類にBT剤+展着剤を霧吹きで散布。
併せて除草 - 生育段階的に必要なものは追肥・中耕・土寄せを実施
12:30-13:00 ニンニク植え付け準備
- 鱗片の外皮を外して選別(病斑・傷の除外)
13:00-13:30 播種(キャベツ PhaseB)
- 72穴セルトレイ×2枚に播種・覆土・潅水
14:00-15:30 ニンニク植え付け
- 黒マルチ使用、条間約20cm/株間15cm、3条配置
- 先端を上にして植え付け、鎮圧・初期潅水
16:30-17:15 播種(ダイコン Phase4)
- サラダ向けミニ大根を播種、覆土・鎮圧
17:15-18:00 元肥施肥
- ラディッシュ(Phase4)・リーフレタス(Phase4)に元肥散布
- カブ(Phase5)に元肥施肥・表層混和
本日のTopic 追い播種はすべきではない
前提:畝A(Phase N)が“歯抜け”になる状況
- 発芽率が低い、食害、管理不良などで途中枯死が発生し、畝Aが歯抜け状態になる
- 次の手順は本来、畝BにPhase N+1を播種・定植し、畝Aの反省を活かして改善する流れ
よくある誘惑:畝Aに「追い播種」で取り戻す案
- 畝Aの歯抜け部分へPhase N+1を同時期に追い播種すれば、総収量を回復できそう
- 同じタイミングで播種するなら準備の無駄は少ない、以後の管理も“ついでに”できそう…という発想
- 「これで、、これで取り戻せるんだ、、、!」というカイジ的な悪魔の声がささやく
結論
- 1年目は追い播種は行わない方がよい
- 目先の収量よりも、オペレーション精度を高めて再現性あるノウハウを蓄積することを優先
追い播種のデメリット
- 計画外の作業が増え、全体のオペレーションが崩れやすくなり、精度が落ちる
- 畝Aの管理が煩雑化(例:追肥・潅水・防除のタイミングが部分的にズレる)
- 生育差による減収(先に育ったPhase Nの葉が陰を作り、Phase N+1の生育が鈍る など)
- Phase Nの収穫終了後も畝Aを次作準備に回せず、回転率が下がる
追い播種のメリット
- 増えるのは“短期の総収量”のみ(改善ノウハウは畝BのPhase N+1で蓄積可能)
まとめ
- 長期的な成長と再現性を重視するなら、追い播種は避ける
- 畝BのPhase N+1で改善を確実に回し、計画通りの運用で“成功パターン”を積み上げる
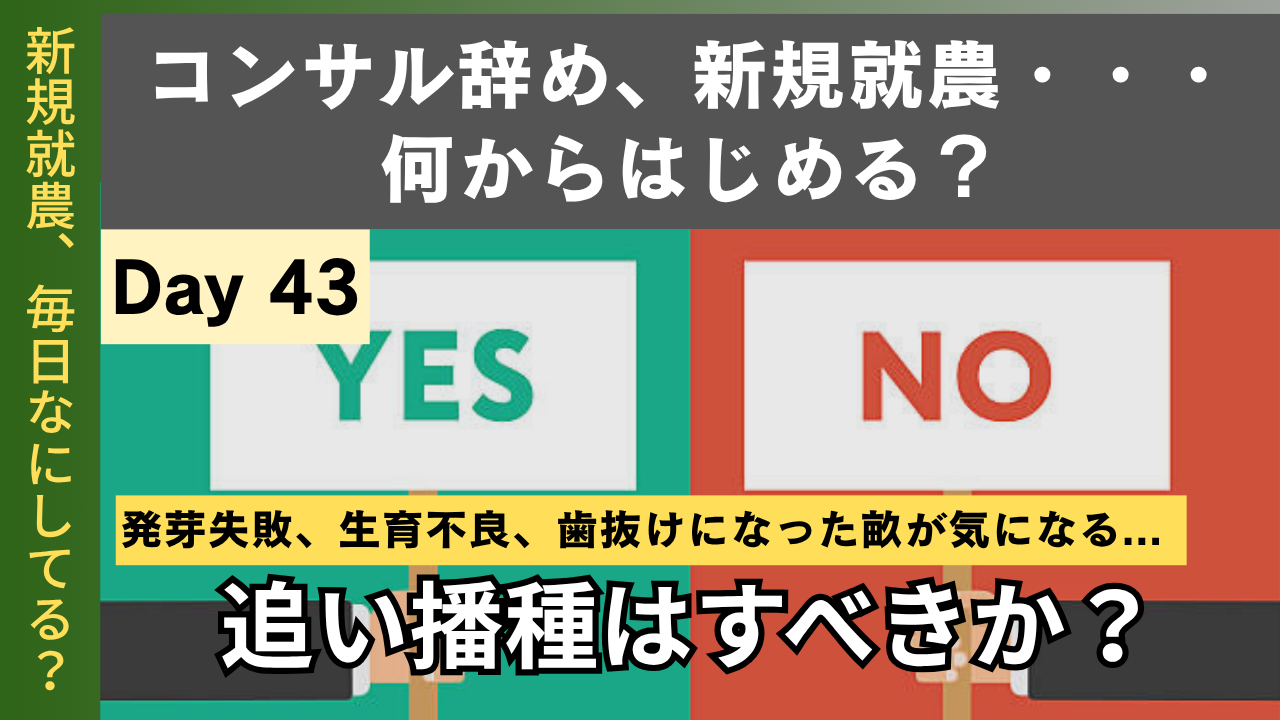
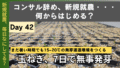
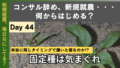
コメント