07:30-09:30 播種
・カーボロネロを播種(固定種)
・茎ブロッコリーを播種(固定種)
09:30-10:00 役所手続き
・会社員から自営業への移行に伴う国民年金・国民健康保険の追加手続き
10:00-11:30 育苗スペース設置(自宅)
・自宅の庭に育苗用の簡易スペースを新設
・ベンチ配置/防虫ネット+必要時の遮光(50%)で環境を整備
・育苗は自宅で行い、定植サイズで圃場へ搬入する運用に切り替え
Remark
・圃場の育苗用トンネル内での食害が多い(昨年まで使用していた住宅地内の圃場の同トンネルと比較して、明らかに有意に多い)。土中からの幼虫・蛹起源が疑わしく、防虫ネットだけでは防げないケースを確認
・耕作放棄地由来の雑草圧=虫圧の高さを実感。圃場内育苗の歩留まりが低下しやすい
・対策の方針
— 育苗は自宅で隔離管理:虫の侵入経路徹底的に遮断
— 持ち込み物の衛生管理:培土・トレイ・ポットは保管場所を分離、使用後は洗浄・乾燥
— 圃場側は定植後のケア重視:初期潅水/活着観察/必要に応じてBT剤散布
— 雑草圧の恒常対策:周縁の刈払い頻度アップ、播種前の火炎処理は“畝表面のみ有効”と理解した上で運用
・その他、耕作放棄地を使用する場合のリスクを以下に整理
【耕作放棄地の主要なリスク一覧】土壌・水利
- 雑草種子バンクの巨大化、多年生・地下茎型(スギナ、チガヤ等)の定着
- 土壌病害の温床(根こぶ病、萎黄病、白絹病などの土壌残存リスク)
- 表層硬化・不均一な団粒、局所的な踏圧・排水不良スポット
- pH・養分の偏り、塩基飽和の低下、微量要素欠乏/過剰の斑
- 暗渠・用排水設備の破損、用水の慣行や取水権の不透明さ
→ 初動:土壌簡易診断(pH・EC・硝態N)→スポット改良、排水溝掘り直し、暗渠位置の可視化
害虫・病害・野生動物
- 雑草圧に伴う虫圧の高さ(コナガ、ヨトウ、ハモグリ、アブラムシ等の増殖源)
- 土中の蛹・幼虫の越夏越冬、トンネル育苗でも食害に遭うリスク
- 獣害(シカ・イノシシ・サル)と足跡(獣道)残存、侵入経路多数
→ 初動:周縁の徹底刈払い、定植直後のBT等の初期防除、電気柵や簡易バリケードの仮設
インフラ・アクセス
- 進入路の狭小・ぬかるみ、駐車・転回スペース不足
(牛糞堆肥業者の大型トラックが入れなったのは痛かった!!!) - 電源・水源の未整備、動力ポンプ・雨水貯留の仮設必須
- 区画杭・境界不鮮明、測量のやり直し負担
→ 初動:最低限の動線設計(車両導線・資材置場・育苗置場)と仮設インフラ計画
法務・地域慣行
- 所有者不明土地・相続未登記、賃貸借の契約不備リスク
- 農地法手続き、農業委員会・水利組合・自治会との慣行参加(清掃・用水負担金 等)
- 農道の通行慣行や共同利用資産の取り扱い不明確
→ 初動:契約書の整備、関係団体への挨拶・加入、費用と作業当番の確認
コスト・オペレーション
- 開墾・整地・残渣処理・伐根など立ち上げコストの過小見積もり
- 長尺資材の端材ロス、調達回数の増加、段取りの複雑化
- 機械外注の頻度増(耕うん・粉砕・運搬)と天候待ちによる遅延
→ 初動:“仮運用→本運用”の二段階計画、週次の資材・作業バッチ化、外注単価の事前相見積り
安全・衛生
- 破片・廃材・不法投棄物の混入、ガラス・金属・ビニールの残留
- ハチ・ヘビ・ダニ等、人的リスク
→ 初動:全面歩査とゴミ回収、危険エリアのマーキング、季節リスクの周知
景観・ブランド
SNS・販売面での写真素材の取りづらさ
→ 初動:外周“見せ場”の先行整備、定点ビフォー/アフターの可視化
荒れ地イメージの残存による来訪者・近隣の印象悪化
13:30-15:00 播種
・タマネギ(黄・固定種)を128穴セルトレイに播種
・鎮圧→潅水→育苗環境へ設置
15:00-18:30 播種(葉物)
・ほうれん草(Phase2)
・スイスチャード(Phase2)
・ビーツ(Phase2)
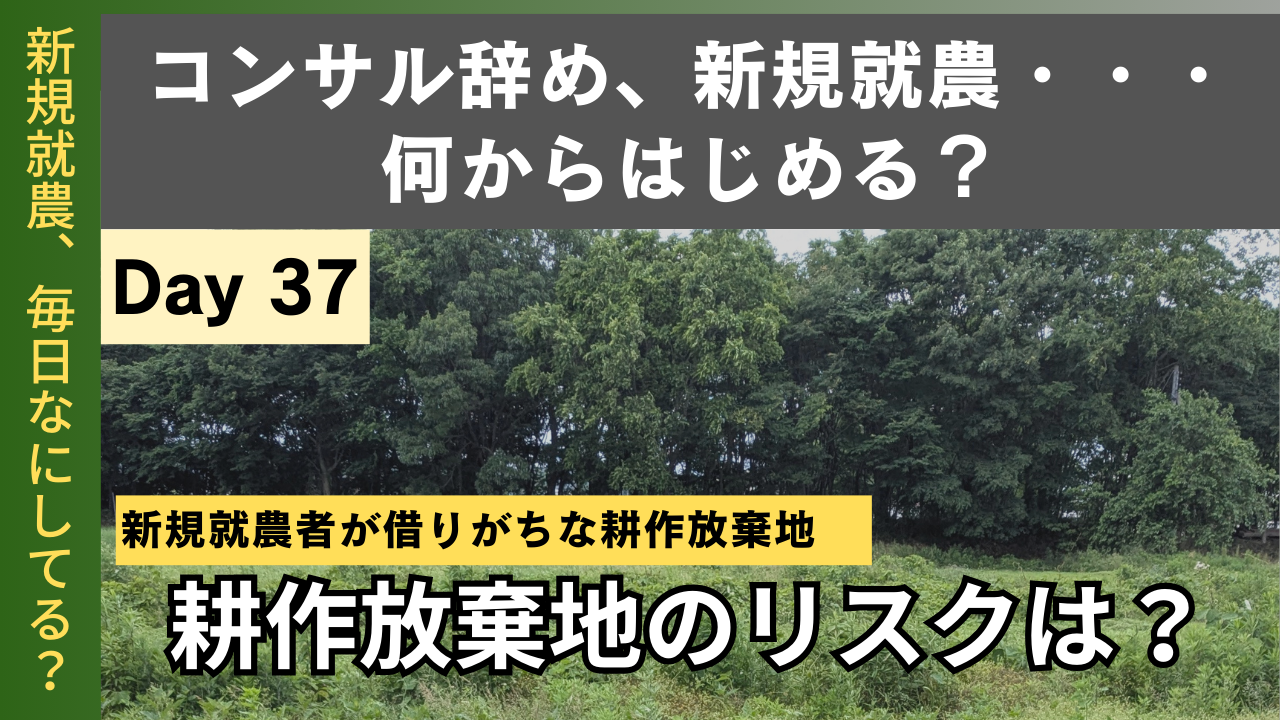
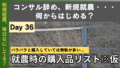
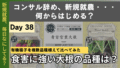
コメント