午前は雑草処理、午後はInstagram用の自己紹介リールの台本作成。
本日のトピックとして、リール台本作成を通して、「私はなぜ農業の道を選んだのか」について振り返りました。
08:00‑09:00 潅水
・ニンジン(播種済)への潅水
・キャベツ・ブロッコリー類(育苗中)への潅水
09:00‑09:30 マルチ補修
・風で剥がれた透明マルチを補修
・マルチ押さえを追加して再固定
09:30‑11:00 雑草対処
・トーチバーナーを使用したFlame Weeding(表面焼き)
・マルチ外の雑草を重点的に処理
06:30-07:30 14:00‑16:00 Instagramリール台本作成
・Instagram用自己紹介リールの台本を検討
・文章作成を通じて、自身のキャリア・価値観・農業を選んだ理由を振り返る
🧭 なぜ農業を選んだのか
今回の台本検討では、自身のキャリアや価値観を再確認しました。以下に整理して記録します。
🎓 農学部進学の原点
高校時代、「日本の食料自給率が大きな問題になる日が来る」と予感し、京大農学部に進学。
しかし在学中は、能力や情熱の面で自信を失い、「ふつうに就職しよう」と方針転換。
🧑💼 コンサル時代と転機
外航海運 → Deloitte → EYとキャリアを重ねるなか、家庭菜園との出会いが転機に。
スーパーで売られている野菜が、ごく限られた「売れ線」「陳列しやすさ」重視の品目・品種に偏っている現実を実感。
🧠 課題意識の醸成
農業関係者との交流や読書を通じて、
「味より見た目」「大きく育つと売れない」などの商流ルールが、美味しさや多様性を殺している構造を知る。
また、
・滋賀県の農業地帯に住みながら、スーパーで他府県の野菜を買う人々
・高い物流コストや中間マージンで鮮度も価格も損なわれている構造
に違和感を覚える。
🔍 社会構造と対比
・米国では「安全保障」の観点から行政が食料自給を下支え
・欧州では「共通農業政策(CAP)」+市民の食の共同体意識により支えられている
・対して日本では、行政も市民も守る力が弱く、農の多様性が失われていく
🤝「人と野菜との関係」への問い
「人と野菜との関係、つまらなすぎない?」という疑問を持つように。
もっと多様で、美味しくて、ストーリーがあって、楽しい野菜との関係があるべきだと思う。
🛠 解決の方向性
①「流通のハック」
地産地消や多様な野菜の自給を進めるには、
中間マージンを排し、ある程度まとめたストックポイントに野菜を届ける「合理的な仕組み」が必要。
例:
・中間業者を減らす(マージン↓)
・複数家庭が受け取れる拠点に集約(物流コスト↓)
・それでいて不便すぎない場所に配置(利便性↑)
②「体験やエンタメによる価値再発見」
価格感度の高い時代でも、体験やエンタメには価値が見出される。
「野菜×エンタメ」の取り組みを通じて、
土に触れ、育て、味わう楽しさを広げたい。
例:
・農業体験イベント
・農泊・収穫ツアー
🎯 ビジョンと展望
- 富裕層向けに閉じない。社会課題の解決にはマスの動きが必要。
(富裕層向けに高級野菜を売る、という方向に逃げない) - ①生産者として現場を深く理解する:美味しい野菜を届け、現場の課題を可視化
- ②需要側・供給側の構造改革へ展開
→「流通のハック」「体験・エンタメ」「未知の第三の道」を模索し、社会実装
→ ノウハウをオープンにして、他地域に広げる
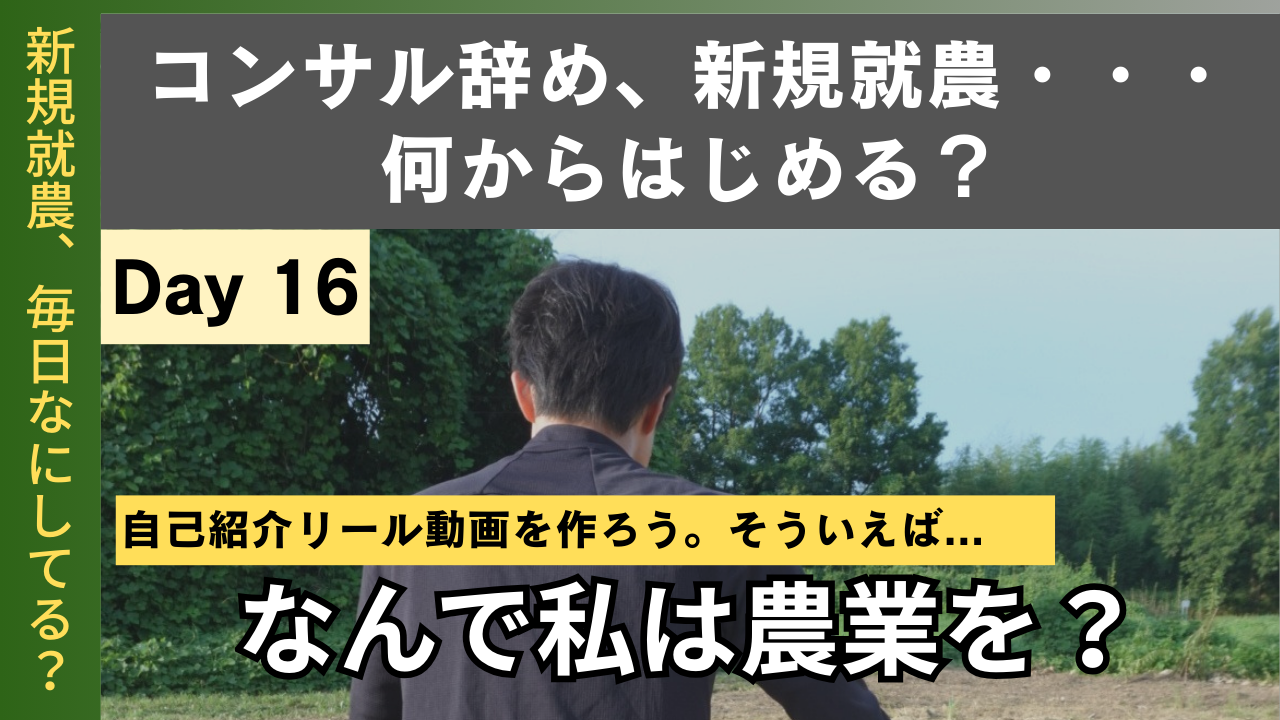
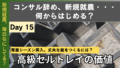
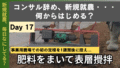
コメント