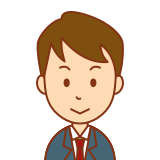
不耕起栽培には「ブロードフォーク」っていう道具を使うことがあると聞いたんだけど、実際のところどうなの?
こんな人のための記事です。
不耕起栽培の普及が日本に先行する海外ではブロードフォークがよく使われていますよね。
ブロード=Broad=幅が広い
フォーク=Fork=又にわかれているもの
という読んで字のごとく、幅が広いフォークのような見た目です。


こちらが当農園で使用しているブロードフォークです
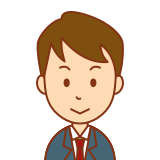
本当にふつうのフォークみたいな見た目なんだね

このようにフォークを差し込んで軽く土を持ち上げて使います。
土壌の「層」を崩さずに土中に新鮮な空気を送るイメージですね
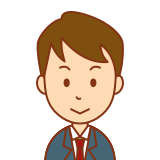
空気を送ることでどんないいことがあるのか気になってきた

この記事ではブロードフォークを使うメリット、注意点、実際に使用してみてどうか?などをお伝えします。参考にしてください!
脱サラ新規就農を考える会社員の方のお役に立てば幸いです。
ブロードフォークとは?基本構造と役割
ブロードフォークの基本構造
ブロードフォークは、手動で土をゆるめるための農具で、不耕起栽培(ノー・ティル)や有機農法を実践する農家に広く使われています。構造はシンプルで、地中に刺さる金属製の歯(ティン)と、両手で握って操作する横長のハンドルで構成されています。
特徴的なのはその歯の形状で、Neversink Farm(当ブログでよく参考にしている、アメリカ有数の反収を誇る有機農場)でも紹介されているように、ナイフ状ではなく「丸くて太い」歯が推奨されています。これは、土壌を切るのではなく「持ち上げる」ようにして作業するため。
結果として、土壌構造を壊さずに作業できるのが最大のポイントです。トラクターのようにエンジンを使わず、静かで人力作業にも適したツールです。
ブロードフォークの使い方
使い方は非常にシンプルで、畝の上に立ち、ブロードフォークを垂直に土へ差し込みます。足で踏み込んで歯を地中にしっかりと埋め込んだ後、ハンドルを手前に引いて軽く土を持ち上げるだけ。この操作を一定間隔で繰り返すことで、耕さずに土をゆるめることができます。
ポイントは「深く刺して、ほんの少し持ち上げる」こと。深く掘り返したり、かき混ぜたりはしません。操作は一見単純ですが、力の入れ方や間隔などには慣れが必要です。使い慣れると、最小限の動作で最大の効果が得られる省力的なツールになります。
ブロードフォークは土壌層を反転させずに土をふかふかにする
ブロードフォークの大きな特徴は、土壌の「層」を乱さずに、やさしく土をゆるめることです。従来の耕うん機のように土を反転させると、地表にいた微生物やミミズが下層へ追いやられ、逆に深層にいた嫌気性の微生物が表層に出てしまいます。これは微生物の住環境を壊し、土壌の健康を損なう大きな原因となります。
ブロードフォークはこのような層のかき混ぜを起こさず、表層〜中層に「空気の通り道」をつくることが目的です。差し込んで少し持ち上げるだけの動作で、土が割れるように緩み、空気を抱き込む“すき間”が自然に生まれるのです。これにより、土中のミミズや微生物の活動を活発にすることが可能です。
例えばミミズはこのふかふかになった通気性のある土の中を自由に移動し、自ら通気孔を広げ、有機物を分解し、団粒構造をつくり出すという循環が始まります。つまり、ブロードフォークで空気を通した瞬間から、土中の生きものたちの営みが活性化し、自然とふかふかの土に育っていくのです。
日本でも入手が可能
国内でもブロードフォークは入手が可能です。当農園では100年以上続く歴史ある鍛冶屋である山崎製作所のブロードフォークを使用しています。
日本の有機農家のニーズに応じて設計されており、特に小規模農地や家庭菜園にも対応したサイズ感や扱いやすさが評価されています。海外製に比べて軽量で、日本人の体格や畝幅にもマッチしており、導入のハードルが低いのも魅力です。
Neversink Farmのような海外の事例でも推奨される「丸くて太い歯」の設計思想を受け継いでおり、日本で不耕起を始めたい人にとって最初の一本として非常におすすめできます。オンラインでも入手可能です。

ブロードフォークを使うメリット
土中の生き物・微生物に新鮮な空気を供給できる
ブロードフォーク最大のメリットのひとつは、土中の好気性微生物やミミズなどの生物に“新鮮な空気”を届けられることです。ブロードフォークは「土を混ぜる」のではなく、「持ち上げることで空間をつくる」道具。その隙間に空気が入り、酸素が微生物の活動を活性化させます。
空気があることで、有機物の分解がゆるやかに進み、団粒構造の形成が進みます。この構造が、さらに通気性と保水性を高め、好循環が生まれます。酸素がなければ土の中は嫌気的になり、腐敗や病害が増えるリスクも。耕さずに通気性を高める手段として、ブロードフォークはまさに理想的なツールなのです。
土中の岩を見つけることができる
見落としがちですが、ブロードフォークは「岩探し」のツールとしても非常に優れています。春先のブロードフォーク作業は「岩を取り除く工程」も兼ねます。使っていると、「ゴン」と手応えがある箇所があり、それが岩の存在を示してくれます。こうした物理的な障害物を初期段階で除去しておくと、その後の作業が格段にスムーズになります。
特に不耕起栽培では、ロータリーやディスクで岩を砕いたり跳ね飛ばすようなことがないため、人力での除去は重要な改善作業です。いったん取り除けば、その岩はもう戻ってくることはありません。長期的に見れば、岩を見つけて排除することは「土壌への投資」とも言えるのです。
堆肥や肥料の一部を土中深くに届けられる
ブロードフォークを施したあとの畝には、小さな縦穴が連続的に生まれます。そこに撒かれた堆肥や肥料の一部が、自然とその縦穴を伝って深層へと浸透していきます。Neversink Farmでも、「施肥前にブロードフォークを入れる」ことで、改良材の浸透を促進していると語られていました。
これは耕すことなく、地表から中層までの養分供給を行うスマートな方法です。ノー・ティル農法では基本的に施肥も表層に行いますが、ブロードフォークを使うことで微生物の活動が届く範囲が広がり、土壌全体のバランス改善につながります。耕すことなく、しかし深く養分を届けたい――そんな要望に応えるテクニックです。
根菜類の収穫にも役立つ
人参や大根などの根菜類の収穫では、誤って作物を傷つけてしまうのが初心者にとって大きな悩みのひとつです。**この問題も、ブロードフォークが解決してくれます。畝の端からブロードフォークを差し込み、やさしく持ち上げることで、根菜が自然に抜けてきます。
この方法なら、収穫物にストレスを与えることなく、美しく抜き取ることができます。また、手や小さなスコップよりも広い面積に一度で力を加えられるため、収穫効率も向上します。とくに市場販売や野菜セットに出荷する際には、見た目のよい根菜を揃えることが品質管理上とても重要。その意味でも、ブロードフォークは「収穫補助ツール」としても価値が高いのです。
ブロードフォークを導入する際の留意点
やりすぎないこと(効果と労力のバランスの見極め)
ブロードフォークは便利な道具ですが、「とにかくたくさん使えばいい」というものではありません。ブロードフォーク作業は見た目以上に体力を使います。しっかりと差し込み、持ち上げる動作を繰り返すにはそれなりの負荷がかかるため、土の状態を見極めながら、必要な場面だけで使うのが賢いやり方です。
特に、すでに土がよくほぐれている場合や、団粒構造が形成されている畝では、無理にブロードフォークを入れても得られる効果はごくわずか。むしろ、「作業量に対して成果が少ない」状態になりがちです。
重要なのは、「やるべきとき」と「やらなくていいとき」を判断すること。作業時間と労力、そして得られる改善のバランスを考えることが、持続可能な土づくりにつながります。
農地が成熟してくると必要性は減る
ブロードフォークは、農地のスタートアップ期に非常に頼りになる道具です。固く締まった土をやさしくほぐし、空気の通り道を作ってくれるので、微生物やミミズが活動しやすい環境が整います。
しかし、Neversink Farmのように不耕起を長年続けていくと、土そのものが呼吸できる状態になっていきます。
いわば、ブロードフォークが担っていた役割を、土自身が自然にこなすようになるのです。
そうなれば、以前のように頻繁にブロードフォークを入れる必要はなくなり、むしろ過剰な作業になることもあります。
ブロードフォークは一時的に活躍するツールであり、永遠に使い続けるものではありません。土の成熟に合わせて手を引いていくことも、農家として大切な判断力のひとつです。
実際に使用してみてどうか?
しばらく耕作していなかった農地では歯の通りが悪い
ブロードフォークは「手動で土をふかふかにする理想のツール」として知られていますが、すべての圃場でスムーズに使えるとは限りません。実際、私がブロードフォークを使用している借地は、長い間有機物の投入や野菜の栽培が行われておらず、ここ数年は雑草をすき込むための耕うんのみで管理されていました。そのため、土の中に微生物が少なく、有機物も蓄積されていない「締まりのある状態」になっており、表面は雨による浸食で固く締まりやすい傾向にあります。
このような未成熟な圃場でブロードフォークを使ってみたところ、片足で体重をかけた程度では歯が最後まで刺さらないことが多々ありました。
しっかりと土の奥まで届かせるには、それなりの工夫と力が必要になるというのが正直なところです。

土が成熟していない農地では、何回か押し込んだり、
両足で全体重をかけたりする必要があります
歯の通りが悪いと、重労働かつ作業時間がかなりかかる
ブロードフォークを思いどおりに機能させるためには、「歯が地中にしっかり入ること」が大前提です。しかし土が締まっていると、これがなかなか難しい。私の農地でも、歯を完全に差し込むためには、ブロードフォークに全体重を預けるようにして踏み込む必要がありました。
この一連の作業を数十センチごとに繰り返すのですから、当然、肉体的にはかなりの負担がかかります。作業ペースも遅くなり、1畝仕上げるのに予想以上の時間がかかってしまうこともしばしばです。
それでも、Neversink Farmのように長期的な土づくりを目指すなら、今は「踏ん張りどき」だと捉えるしかありません。土が変わるには時間がかかるもの。今の労力は、未来のふかふかの畑への先行投資と信じて、コツコツ続けていきたいと思います。
ブロードフォークを使ってふかふかの土をつくろう
「土を耕さずに、でもしっかりと“耕されたような”状態をつくりたい」——そんな矛盾を解決してくれるのが、ブロードフォークです。Neversink Farmのような不耕起栽培の先進農家では、ブロードフォークを通じて“耕す”のではなく“育てる”という土づくりの考え方が徹底されています。
表面をかき混ぜるのではなく、歯をまっすぐ差し込み、ほんの少し持ち上げるだけ。
この静かでやさしい動作が、土に空気を届け、微生物やミミズの活動を促し、やがては耕さなくてもふかふかの土が保たれる自立した環境へとつながっていきます。
もちろん、使い始めの頃は重労働に感じることもありますし、結果がすぐに目に見えるわけではありません。しかし、「土は育てるもの」という視点を持って毎年少しずつ改良を積み重ねていけば、3年後、5年後にはスコップがすっと入るような理想の土に近づいていくはずです。
自然に寄り添った農業を志すなら、ブロードフォークは間違いなくその第一歩。
ぜひ、自分の畑でもこのシンプルで力強い道具を取り入れて、未来につながる“ふかふかの土”づくりを始めてみてください。
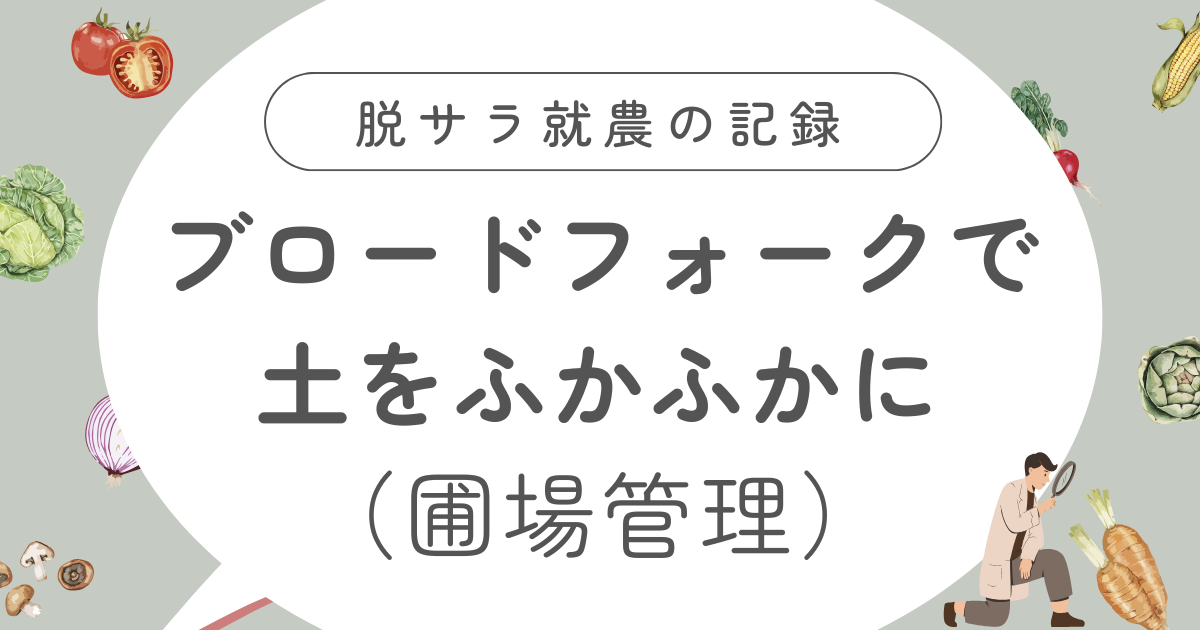
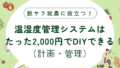

コメント