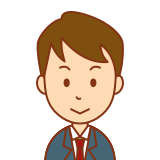
農業を始めたいけど、「農業の時給は400円」なんていう記事もあったりして、それな会社員を続けていた方がいいなと思ってしまうな。。。
こんな人のための記事です。
農業の時給が低いという話はよくききますよね。
試しに「農業 時給」でgoogle検索してみると、1ページ目にこんな記事が目に入ります。
「米農家の「時給」、23年は97円」
「農家は時給換算で379円?」

ほ、ほんとうならかなり苦しいですね、、、😢
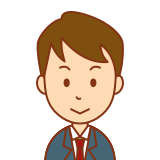
やっぱり脱サラ農業なんて現実的じゃないなあ

私は300㎡のスモールスタートで農業を始めましたが、かかったコストを元に「結局どれだけ野菜を売れば採算がとれるのか?」を考えてみました!
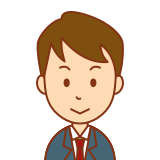
結局どれだけ売ればいいの?

目標収益を考えるには、P/L(損益計算書)をボトムアップで積み上げて考える方法が有効です。簡易的に計算しますので、参考にしてください!
農業経営において、成功のカギとなるのは「どれだけ売れるか?」ではなく、「どれだけ売るべきか?」という視点です。本記事では、300㎡の畑で目指すべき収益を明確にし、具体的な売上目標を設定する方法を解説します。また、先行プレイヤーの反収を参照しながら、その目標に実現可能性があるのか?についても考えます。
脱サラ新規就農を考える会社員の方のお役に立てば幸いです。
採算は「あるべき姿」から考え、「できる/できない」は考えない
農業経営において、多くの人が「どれだけ売れるか?」から計算を始めます。しかし、それでは採算をとるのが難しくなります。本当に考えるべきは、「どれだけ売るべきか?」という視点です。本記事では、収益のあるべき姿から逆算する考え方を解説します。
「どれだけ売れそうか」の考え方を排除する
多くの人は、現実的な販売見込みから売上目標を設定しようとします。「おそらく月に50セットは売れるだろう」「知人やSNSを使えば100セットは行けるかもしれない」といった発想です。しかし、この考え方では、現実のコストや目標とする収益が後回しになり、最終的に「頑張っても利益が出ない」という状況になりかねません。
売上の目標を「できるかどうか」ではなく、「必要な金額を稼ぐにはどれだけ売らなければならないか?」の観点から考えることが重要です。これは、事業として農業を持続させるための必須の考え方です。例えば、報酬を時給2,500円と設定し、次年度への投資資金を確保する場合、そのために必要な売上高を計算することが最優先になります。農業の生産性は短期間で大きく変えられませんが、販売戦略を組み立てることで売上の目標達成は可能です。
先に決めるべきは「どれだけ売るべきか」
持続可能な農業経営を目指すには、「販売見込み」ではなく「必要な売上」から逆算する考え方が必要です。これは、P/L(損益計算書)のボトムラインから組み立てるアプローチです。
まず、目指すべき報酬を決めます。私は農業を専業とする上で、時給2,500円という水準を目標に設定しました。この金額には税金や社会保険料の概算も含めています。これを年間の労働時間に掛け算し、最低限確保すべき報酬額を算出します。
次に、次年度の投資に必要な資金を考えます。設備投資、種苗費、販促費など、事業を継続するために必要な費用は毎年発生します。私は、報酬と同額の利益剰余金を確保することを目標としました。
最後に、日々の農業運営にかかるコストを積み上げます。地代・資材費・通信費・広告費など、農業経営には様々な固定費と変動費がかかります。これらのコストをすべて足し合わせると、最終的に必要なRevenue(売上)が明確になります。
必要なRevenue=次年度投資用の利益+報酬+コスト
売上の目標を決める際に重要なのは、「次年度投資用の利益」「報酬」「コスト」の3つを合計することです。この3つを明確にすれば、事業として成り立つ売上目標が見えてきます。
- 次年度投資用の利益: 設備投資や拡張のために、年間の売上の一部を再投資する
- 報酬: 自分の労働に対する対価(時給2,500円 × 労働時間)
- コスト: 種苗費・資材費・運営コスト・広告費・固定費など
例えば、半年間の農業運営でこれらを計算すると、必要なRevenue(売上高)は約100万円となります。この数字を元に、どれだけの野菜セットを販売すればよいのかを逆算し、実現可能な販売戦略を立てることができるのです。
このように、「あるべき姿」から考え、実現のための方法を後から組み立てることで、持続可能な農業モデルを構築できます。次の章では、実際に300㎡のスモールスタート畑で「どれだけ売るべきか」を具体的に試算していきます。
300㎡のスモールスタート畑で「どれだけ売るべきか」
300㎡の畑での農業運営を通じて、実際にどれだけの売上が必要なのかを具体的に試算していきます。ここでは、半年間の実績データをもとに、必要なコスト、目標とする次年度投資利益と報酬、最終的に目指すべき収益について詳しく解説します。
半年間の畑運営でかかったコスト
半年間の農業運営において、実際に発生したコストを整理すると、以下のようになります。
- 地代・賃借料: 5,000円
- 減価償却費: 20,000円
- 車両維持費: 20,000円
- 通信費: 45,000円
- 燃料費: 20,000円
- 消耗品費: 5,000円
- 広告宣伝費: 23,000円
- 売上原価(種苗費・肥料費など): 110,000円
合計すると、半年間の運営コストは約248,000円となります。なお、「荷造運賃」「荷造梱包費」は販売価格に別途転嫁し、収益にもコストにも含めていません。
コストを抑えるためにいくつかの工夫を行っています。例えば、軽トラは中古のものを安価で購入し、減価償却費の抑制に貢献しています。また、農機具類はレンタルを多用することで、初期投資を抑えながら運営を進めています。今後、圃場は2,000㎡程度に拡大する予定ですが、Neversink Farmの管理手法に倣い、トラクターは購入せず、人力と小型機械で対応する方針です。
年間一括で支払うコストについては、半年分として計上し、キャッシュフローを考慮しながら適正に管理しています。
目指す次年度投資用利益/報酬/投下時間
私は、事業の成長と安定のために、利益の半分を次年度の投資資金として確保する方針をとりたいと考えています。農業を持続可能な事業として成長させるためには、次年度以降の投資が欠かせません。特に、IoT機器の導入によるデータ活用やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することで、作業の効率化や収穫量の安定化が期待できます。
例えば、センサーを活用した土壌管理や、水管理の自動化などが挙げられます。また、土壌試験もより精緻に行い、野菜の品質向上を図りたいと考えています。これらの技術を活用するためには、継続的な設備投資が必要となるため、毎年一定の利益剰余金を確保することが重要です。
また、報酬についても明確にしておく必要があります。私の報酬水準は時給2,500円と設定していますが、これは税金や社会保険料を考慮した上での金額です。実際の手取り額ではなく、あらかじめ税金分をざっくり上乗せしているため、個人事業としての収入計画が立てやすくなります。
労働時間の設定についても、長期的な視点で考慮しています。私は今後2,000㎡規模の農地を運営する予定であり、年間2,000時間の労働時間を投入する計画です。現在の300㎡の畑では、単純にこの比率で割り戻し、年間300時間、半年で150時間を投下する前提で試算しています。実際には、300㎡と2,000㎡では作業効率が異なるため、生産性の違いを考慮する必要がありますが、現時点で300㎡の生産性に基づいて計算しても意味が薄いため、2,000㎡の基準を用いるのが合理的です。
これらをふまえると、以下のような試算結果となります。
- 報酬: 2,500円 × 150時間 = 375,000円
- 次年度投資用利益: 375,000円
300㎡の畑で目指すべき収益は?
以上を踏まえると、300㎡の畑で目指すべき収益は以下の計算となります。
ざっくり年間200万円の収益が必要ということになりますね!
半期:998,000円 = 次年度投資用益(375,000円)+報酬(375,000円)+Cost(248,000円)
通期:1,996,000円 = 998,000円 × 2
当然200万円分の価値を顧客に提供する必要がある
勘違いしてはならないのは、私たちは200万円分の価値を顧客に提供する必要がある、ということです。この記事では持続的に事業を営む上でボトムアップ式にP/Lを試算しておくことの重要にフォーカスしていますが、そこで目指す収益を顧客からいただくためには、どのようなサービスを提供するべきか?このテーマと向き合うことを忘れてはなりません。
目指すべき収益の実現可能性
Neversink Farmの反収を考えると、野心的だが実現可能性はある
Neversink Farmは、小規模農業の成功例として広く知られています。この農場は約6,000㎡(1.5エーカー)の敷地で年間5,300万円の売上を達成しています。単純に100㎡あたりの売上を計算すると、およそ88.3万円/年となります。(※1ドル=150円)
一方、私の300㎡の畑で目指す売上は、通期で約200万円です。これは100㎡あたり66.5万円/年に相当し、Neversink Farmの水準の約75%に達します。したがって、Neversink Farmの収益モデルを参考にしながら効率的な農業経営を行えば、この目標が十分に実現可能であると考えられます。
(※米国の物価は日本と比較して高いことが知られているが、野菜に関して言えば平均的には大きく水準が変わらないと言われています。また、慣行栽培と有機栽培の相対価格も日本と同程度と言われています)

改めてNeversink Farmの反収はすさまじいですね。
しかし希望がもてます!
もちろん、Neversink Farmは高度な栽培管理技術や市場戦略を駆使しており、そのままの運営手法を適用するのは難しいかもしれません。しかし、密植栽培や高収益作物の選定、作業の効率化といったノウハウを取り入れることで、私の300㎡の圃場でも同様の売上を達成することは十分に可能です。
また、Neversink Farmは高品質な作物を安定供給するために、生産プロセスの合理化や流通の効率化を進めています。これに倣い、私も農作業の効率化と販売戦略の強化を行うことで、100㎡あたり66.5万円/年という目標を達成する道が開けるでしょう。
ビジネスモデルを野菜セットD2C販売とした場合の試算
野菜セットのD2C(Direct-to-Consumer)販売は、小規模農家にとって有力な販売手法の一つです。このモデルでは、仲介業者を挟まずに消費者へ直接販売することで、利益率を高めることが可能になります。また、定期購入モデルを活用することで、安定的な売上を確保しやすくなります。
仮に、80サイズ野菜セットを3つの価格帯(2,500円、3,500円、4,000円)で提供することを考えてみましょう。2,500円だとらでぃっしゅぼーや社などが近い価格帯です。3,500円だと有名な久松農園などが近い価格帯ですね。4,000円を超えるとなると、かなりのプレミアム要素が必要となってくるでしょう。
それぞれの場合、以下のような販売数が必要になります。
- 2,500円/セットの場合: 半期で399セット、通期で798セット
- 3,500円/セットの場合: 半期で285セット、通期で570セット
- 4,000円/セットの場合: 半期で250セット、通期で500セット
D2C販売のメリットとしては、顧客との直接的な関係を築ける点が挙げられます。特に、定期購入プランを導入すれば、毎月安定した収益を確保しやすくなります。例えば、2,500円のセットを月4回、春夏シーズン3カ月、秋冬シーズン3カ月の計6カ月配送するモデルを採用すると、1顧客あたり年間6万円の売上が見込めます。この場合、必要な売上を達成するためには83人程度の顧客を見つける必要がある、ということになります。
また、販売チャネルとしては、自社ECサイト、SNSマーケティング、地元のマルシェや宅配サービスとの提携など、多様なアプローチが考えられます。特に、InstagramやLINE公式アカウントを活用したマーケティングにより、リピーターを増やしやすくなります。
このように、D2C販売モデルを採用することで、価格設定に応じた販売数を達成することが現実的に可能となります。最適な販売戦略を組み合わせることで、300㎡の圃場でも年間200万円の売上目標を達成する道が開けるでしょう。
このの収益性は一般的な日本の農業の感覚からするとかなり高い部類に入ると思われ、現実的でないのでは?という感覚をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、Neversink Farmのような実際に実現している先行事業者がいる以上、そこに達しないのは経営者側のスキル不足ということになります。繰り返しですが積み上げ式の思考ではなく、あるべき姿から逆算した戦略検討が必要になります。

脳に汗をかくほど戦略を考えに考えなければ、、!
おわりに:「あるべき姿」P/Lを積み上げ、目標を明確化しよう
農業経営において、成功のカギとなるのは「どれだけ売れるか?」ではなく、「どれだけ売るべきか?」という視点です。本記事では、300㎡の畑で目指すべき収益を明確にし、具体的な売上目標を設定する方法を解説しました。
必要な売上を計算することで、価格設定や販売数の目標が明確になります。また、Neversink Farmの成功事例からも、小規模農業で十分な収益を上げることが可能であることがわかります。
しかしここまでは絵にかいた餅です。
今後は、販売チャネルやマーケティング施策をより具体的に計画し、実際の販売戦略を構築することが重要です。持続可能な農業を実現するために、「あるべき姿」から逆算したP/Lを基に、目標達成に向けたアクションを積み上げていく必要があります。
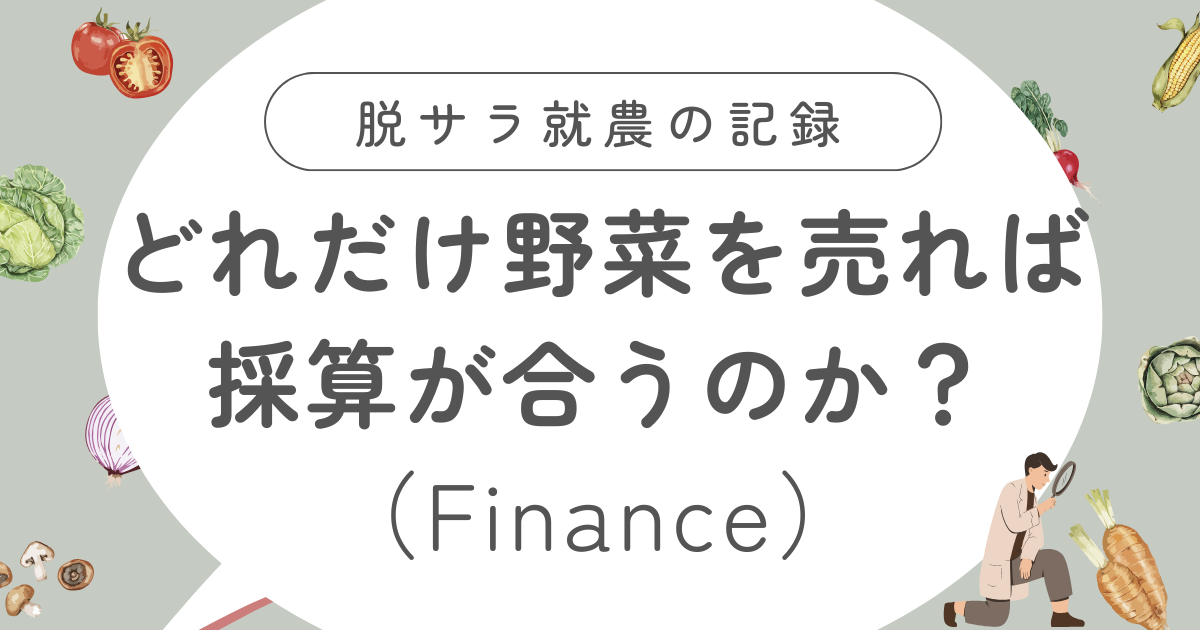

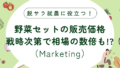
コメント