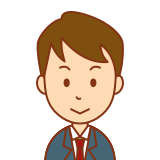
もう農協に卸せばいいって時代ではないことはわかってる。
じゃあどうやって販売先を開拓していけばいいの?
こんな人のための記事です。

直売所やレストランなどの販路開拓も重要ですが、
Webで直接消費者と繋がる販売方法もおすすめです
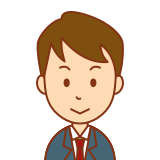
いわゆる産直ECってやつ?
食べチョクとかポケットマルシェとか、、、

スモールスタート*で農業をはじめるなら、Shopifyなどのプラットフォームを使って自前のオンラインショップを構築するのがおすすめです!
*当ブログでは副業として小さく農業を始めることを推奨しています
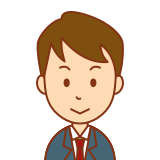
Shopify、、?聞いたことがないな。
自前でショップを構築って、大変だしお金もかかるんじゃないの?

自前のオンラインショップは半日もあれば構築できますし、費用も皆さんのイメージよりかなり安価です。何より、マーケティングの訓練になります!
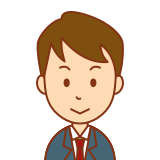
自分にできるとは思えないけど、じゃあ話だけきいてみようかな
脱サラ就農のスモールスタートにオンラインショップは必要?
脱サラして就農を目指す人にとって、一番の関心事は「農作物をしっかり育てられるか?」という点かもしれません。しかし、実際に就農してみると、さらに大きな課題に直面します。それが 「販売の壁」 です。
この壁を乗り越えるためには、スモールスタートの段階から オンラインショップを開設し、Webマーケティングを学ぶことが有効です。オンラインショップの運営を通じて販売の仕組みを学び、実践しながらスキルを磨くことが、成功する農業経営への第一歩 となります。
脱サラ就農を目指す人の多くが直面する「販売の壁」
農業は、作物を作ることだけでなく、それを どのように売るか も非常に重要です。脱サラして新規就農する人の多くは、農産物の販売経験がないため、せっかく育てた野菜や果物を思うように売れないという問題に直面します。
「農協に出せばいいのでは?」と思うかもしれませんが、農協出荷では価格決定権がなく、収益が安定しにくいのが現実です。また、個人で飲食店やスーパーに直接販売する方法もありますが、すぐに契約を獲得できるとは限りません。さらに、道の駅や直売所への出荷は、手数料や競争の激しさが課題になります。
では、どうすれば良いのでしょうか?
答えは 「自分で販売チャネルを持つこと」 です。そのために有効な手段のひとつが オンラインショップの開設 です。
生産技術だけでなく、販売・マーケティングの学習が必須
脱サラ就農者が長く続けていくためには、 「売る力」 を身につけることが欠かせません。生産技術の向上はもちろんですが、同じくらい重要なのが 販売・マーケティングの知識と実践経験 です。
特に、現代では Webを活用した販売戦略 が求められます。SNSを使った情報発信や、ECサイトでの販売、オンライン集客など、農業の世界でもデジタルマーケティングが重要になっています。
しかし、これらのスキルは 一朝一夕に身につくものではありません。だからこそ、スモールスタートの段階から少しずつ実践しながら学ぶことが大切 です。
スモールスタート期間からオンラインショップを開設するメリット
本格的に農業を始める前に、スモールスタートとして少量の作物を栽培・販売する期間を設けることをおすすめします。その際、オンラインショップを開設することには 以下のようなメリット があります。
- Webマーケティングを実践しながら学べる
⇒ ECサイトの運営を通じて、集客・販売の仕組みを理解できる
⇒ SEO(検索エンジン最適化)やSNS運用の重要性が体感できる

例えばShopifyでは、ショップ開設後も次々と出されます。宿題を1つ1つクリアすることでマーケティングが身につくようになっているんですね!
- 低コストで運営できる
⇒実店舗を構えるよりも圧倒的に安く販売を始められる
⇒本格的にEC運営を学べるShopifyのようなECプラットフォームが少ない初期費用で利用できる - 農産物のブランディングができる
⇒「○○農園の野菜はこだわりがあって美味しい」と認知してもらう
⇒収穫や販売の様子を発信し、ファンを増やしておくことで、本格就農後の売上につなげられる
なぜスモールスタートでもオンラインショップを開設すべきか?
「本格的に就農してからオンラインショップを開設すればいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、スモールスタートの段階でオンラインショップを立ち上げておくことで、就農後の販路確保や売上向上につながる重要な学びを得ることができます。ここでは、スモールスタート期間中にオンラインショップを開設するメリットについて詳しく解説します。
低コストでWebマーケティングを学べる
オンライン販売を成功させるためには、Webマーケティングの知識とスキル が欠かせません。しかし、これらは座学だけでは身につかず、実際に運営しながら試行錯誤していくことが重要です。
スモールスタートの段階からオンラインショップを開設することで、以下のような Webマーケティングの基礎 を 低コストで学ぶ ことができます。
学べるポイント
- 商品ページの作成方法(魅力的な写真・商品説明・価格設定)
- SEO(検索エンジン最適化)を意識した商品ページの作り方
- SNSやブログとの連携による集客の仕組み
- メルマガやLINE公式アカウントを活用したリピート戦略
多くのオンラインショップサービス(Shopify・BASE・STORESなど)は、初期費用無料または低コストで始められる ため、大きなリスクを負わずにマーケティングを実践できます。

Webマーケティングをコンサルや講座を通して学ぼうと思うと多額のお金がかかってしまいます。低コストで学べるので私も助かっています
「売る力」を試行錯誤しながら身につけられる
農業を始めると、「作ること」に集中しがちですが、実際に収益を上げるためには「売る力」が必須です。オンラインショップを通じて、どんな商品が売れるのか?どんな売り方をすればいいのか? を試しながら学ぶことができます。
試行錯誤できるポイント
- 価格設定:いくらなら売れるのか?適正価格はいくらか?
- 商品パッケージ・セット販売:単品よりセットのほうが売れる?どんな組み合わせがよいか?
- 販売タイミング:季節ごとに需要が変わる?予約販売は可能か?
- 販売ページの改善:写真や説明文を変えたら売れ行きが変わるのか?
実際に販売してみることで、「自分の野菜が思ったより売れない…」という経験をするかもしれません。しかし、それこそが 成長のチャンス です。失敗や成功を積み重ねることで、徐々に 売るためのコツ がわかってきます。

私も思ったより売れませんでした😢。スモールスタートだと、本業の収入があるうちに試行錯誤できるのが大きなメリットです!
SNSやブログと連携して集客のノウハウを蓄積できる
オンラインショップを開設しても、「お客さんが来ない=売れない」となってしまっては意味がありません。そのため、SNSやブログを活用して集客するスキル も、スモールスタートの段階で身につけておく必要があります。
SNSやブログと連携するメリット
- InstagramやTwitterで 栽培の様子や商品情報を発信 し、ファンを増やす
- ブログで 「こだわりの農法」や「野菜の食べ方」 を発信し、SEO対策をする
- FacebookやLINEを活用して、リピート購入につなげる
- YouTubeやTikTokを活用し、動画で視覚的に魅力を伝える
農作物は 「顔の見える生産者」から買いたい という消費者心理が強いため、SNSやブログを活用することで ブランド力を高め、継続的に集客する仕組み を作ることができます。
オンラインショップを開設していると、SNSからの流入を確認できるため、「どんな投稿が集客につながったのか?」をデータで分析しながら改善できます。この試行錯誤が、就農後の販売活動に大いに役立ちます。

農業者同士のフォロー・フォロワーの輪は比較的広げやすいですが、
本当の潜在顧客にリーチするのは簡単ではないですよね。
実際に開設・運営することで、自分に足りないスキルが明確になる
オンラインショップを運営してみると、思ったように売れない、集客ができない、リピートにつながらない… など、さまざまな課題が見えてきます。しかし、これらはすべて、就農後に直面する課題の縮図 です。
スキル不足を自覚するポイント
| 課題 | 具体的な例 | 必要なスキル |
|---|---|---|
| 商品が売れない | 商品ページを作ったのに全然売れない | 魅力的な商品写真の撮影、キャッチコピーの作成 |
| 集客ができない | Instagramで投稿してもお客さんが増えない | SNSマーケティング、ターゲット設定 |
| リピート購入がない | 一度購入してもらったが、再注文がない | メルマガ・LINE運用、CRM(顧客関係管理) |
| 価格設定が難しい | どの価格帯なら適正なのかわからない | 競合分析、原価計算 |
こうした課題に早めに気づいて改善することで、本格的な就農後にスムーズに販売を拡大できる ようになります。
産直EC vs. 自分でオンラインショップ:どちらがおすすめ?
オンラインで農産物を販売する方法には、大きく分けて 「産直ECを利用する」 か 「自分でオンラインショップを開設する」 という2つの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、スモールスタートで農業を始める場合は、自分でオンラインショップを運営するほうが効果的 です。
ここでは、それぞれの特徴を詳しく比較し、なぜ自前のオンラインショップに注力すべきなのかを解説します。
産直ECのメリット・デメリット
産直ECとは?
食べチョクやポケットマルシェなどのサービスを利用し、農産物を消費者に直接販売できるプラットフォームのことを指します。
産直ECのメリット
- 簡単に販売を開始できる
→ プラットフォームに登録するだけで販売が可能。自前のショップを作る手間が不要 - 既存の集客基盤がある
→ すでに多くの消費者が利用しており、ゼロからの集客を行う必要がない - 決済・配送の仕組みが整っている
→ クレジットカード決済や配送システムが用意されており、初心者でもスムーズに販売できる - 信頼性が高い
→ 産直ECのプラットフォーム自体の知名度があり、初めての顧客でも安心して購入しやすい。
産直ECのデメリット
- 手数料が高い
→ 販売額の 10〜20% を手数料として支払う必要があり、利益率が低下する - 価格競争が激しい
→ 多くの農家が出品しており競争に巻き込まれやすい。価格を下げざるを得ない状況になることも - 顧客リストが手元に残らない
→ プラットフォームの顧客情報を活用できず、リピーター戦略が難しい - ブランディングがしにくい
→ プラットフォーム内では他の生産者と同列に扱われ、独自の魅力を伝えにくい

産直ECは販売実績やレビュー数によって上位表示されるアルゴリズムと推定されます。その中で新規参入者が差別化するのはハードルが高そうですよね
自分でオンラインショップを持つメリット・デメリット
自分でオンラインショップを開設するとは?
Shopify、BASE、STORESなどのECサービスを利用し、自分専用のオンラインショップを構築・運営する方法。
自分でオンラインショップを持つメリット
- 利益率が高い
→ 産直ECのような高額な手数料が発生せず、売上をそのまま利益にできる - 価格設定や販売戦略を自由に決められる
→ 割引キャンペーンやセット販売など、柔軟な販売方法が可能 - 顧客との直接的な関係を築ける
→ メルマガやLINEを活用し、リピーターを増やしやすい - ブランディングができる
→ 「〇〇農園」の名前で販売でき、SNSとの連携によるブランド強化が可能 - 販路の拡大がしやすい
→ 将来的に定期購入モデルや法人向け販売など、多様なビジネス展開が可能
自分でオンラインショップを持つデメリット
- 集客が必要
→ SNSや広告を活用して、自ら顧客を集める努力が求められる - ショップ運営の知識が必要
→ 商品ページの作成や決済・配送管理など、基本的な運営スキルが必要 - 初期の売上が見込めないことも
→ 立ち上げ当初は認知度が低いため、すぐに売上を伸ばすのが難しい

軌道に乗るまでは地道な努力と忍耐が必要です。
短期間で収益源として見込むのは難しいでしょう
スモールスタートで農業を始める場合、自分でショップを運営するほうが効果的
スモールスタートで農業を始める場合、短期的な売上よりも 「ファンを作ること」 や 「ブランドを確立すること」 が重要になります。その観点から考えると、産直ECよりもSNSと自前のオンラインショップに注力したほうが、長期的な成功につながります。
SNSと自前ショップを優先すべき理由
- 産直ECでは競争に埋もれやすく、価格競争に巻き込まれる
- SNSを活用すれば、農園のファンを増やしながら直接販売につなげられる
- 本業がある場合、短期の売上よりも顧客リストの蓄積が最優先
- SNS×自前ショップの組み合わせなら、手数料を抑えながら安定した販売が可能
最適な戦略
- SNS(Instagram、Twitter、YouTube)に注力し、ファンを増やす
- SNSのフォロワーを自前のECサイトへ誘導し、顧客リストを増やす
- フォロワーが増えた段階で、販促を本格化し、売上を伸ばす
4. どのプラットフォームを使うべきか?
自前のオンラインショップを開設する場合、どのプラットフォームを選ぶべきかは非常に重要です。現在、国内で人気のあるプラットフォームには Shopify・BASE・STORES があります。それぞれの特徴を比較し、最もおすすめの選択肢を解説します。
1. Shopify・BASE・STORESの比較
| プラットフォーム | 初期費用・月額費用 | デザインの自由度 | マーケティング機能 | 手数料 | 事業の拡張性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | 初期費用無料 / 月額費用 $5(スタータープラン)〜 $39(ベーシックプラン)〜 上位プランあり | 高い(独自テーマ・カスタマイズ可) | 高い(アプリ連携・分析機能) | 低め(外部決済可能) | 高い(海外販売・拡張性抜群) |
| BASE | 初期費用無料 / 月額費用無料 | 中(テンプレート豊富) | 低め(基本機能のみ) | 高め(6.6%+40円) | 低め(小規模向け) |
| STORES | 初期費用無料 / 月額無料プランあり(有料プラン:月額2,178円〜) | 中(カスタマイズ可能) | 低め(集客機能は限定的) | 高め(3.6%〜5.0%) | 中(中小規模向け) |
この表からもわかるように、それぞれのプラットフォームには向き・不向きがあります。
2. Shopifyをおすすめする理由
スモールスタートの段階でも、長期的な視点で考えると「Shopify」が最も優れた選択肢 になります。以下の理由を詳しく解説します。
本格的なEC運営を目指せる
- Shopifyは、世界中のEC事業者に利用されており、小規模から大規模まで対応可能
- 販売管理、在庫管理、マーケティングツールなど、EC運営に必要な機能が揃っている

Shopifyのマーケティングツールは本当に充実しています!😲
デザインや機能の自由度が高い
- 豊富なテーマ から選べるほか、コードを編集してオリジナルデザインも可能
- アプリを追加することで、決済方法の変更や販売戦略の強化など、機能の拡張が容易
将来的に規模を拡大しやすい
- 他のプラットフォームと違い、Shopifyは事業規模が大きくなっても対応可能
- 追加のアプリやAPI連携により、機能を強化しながら成長させられる
- 一定の売上を超えたら、BASEやSTORESからの移行も発生するが、Shopifyなら最初から拡張を見据えて運用できる
海外販売にも対応しやすい
- 多言語対応、通貨切り替え機能が充実しており、越境ECにも適している
- 世界175カ国以上で利用されており、国内販売だけでなく、海外市場への展開も視野に入れられる

私はまだ着手できていませんが、現在の事業環境下において外貨獲得は当然目指すべき選択肢です。多言語対応や通貨切替対応は嬉しいですね。
Shopifyでオンラインショップを開設するステップ
Shopifyは直感的に操作できるプラットフォームですが、スムーズに開設するためにはいくつかの重要なステップがあります。本章では、Shopifyを使ったオンラインショップ開設の流れを解説します。

半日もかからずに最低限のショップ構築まで(お客様が商品を発注できるようになるまで)たどり着くことができました!😲
1. アカウント作成
Shopifyを利用するためには、まずアカウントを作成します。
- Shopify公式サイトにアクセス。
- 「無料で試す」ボタンをクリックし、メールアドレス・パスワード・ストア名を入力。
- 事業の詳細(業種、販売予定の商品など)を入力。
- Shopify管理画面にアクセスできるようになる。
💡 ポイント
- 3日間の無料トライアルがあるため、気軽に試せる。
- ストア名は後から変更可能だが、できるだけ覚えやすい名前を選ぶ。
2. テーマ選び&デザイン設定
ストアの見た目は、購買率に大きく影響するため、デザイン設定は重要です。
- Shopifyの「テーマストア」から無料・有料のテーマを選択。
- 「オンラインストア」>「テーマ」>「カスタマイズ」でデザインを編集。
- ロゴ、カラースキーム、フォントを設定。
- ホームページ、商品ページ、カートページのレイアウトを整える。
💡 ポイント
- 無料テーマでも十分な機能を備えているが、独自性を出すなら有料テーマも検討。
- モバイル対応を意識して、スマホでの見え方を確認する。
3. 商品登録
商品ページは、お客様が購入を決める上で最も重要な要素です。
- 「商品管理」>「商品を追加」から、新しい商品を登録。
- 商品名、説明、価格、在庫数を入力。
- 高品質な商品画像をアップロード。
- 商品のカテゴリやタグを設定し、検索しやすくする。
💡 ポイント
- 商品説明には、特長や使用方法、こだわりポイントを明記。
- 画像は明るく、複数の角度から撮影すると購買率アップ。
- 在庫管理を有効にして、売り切れ時の対応を設定。
4. 支払い・配送設定
オンラインショップを開設する際に、支払い方法や配送設定も重要なステップです。
支払い設定
- 「設定」>「決済」から、利用する支払い方法を選択。
- 「Shopify Payments(国内主要カード・Apple Pay対応など)」を有効化。
- その他の決済方法(PayPal、Amazon Pay、銀行振込など)を設定。
💡 ポイント
- Shopify Paymentsを利用すると、取引手数料を削減できる。
- PayPalやコンビニ決済など、多様な支払いオプションを用意すると購入率が上がる。
配送設定
- 「設定」>「配送と配達」から、配送ルールを設定。
- 配送エリア・送料・無料配送条件を決定。
- 配送業者(ヤマト運輸、佐川急便など)と契約し、発送準備を整える。
💡 ポイント
- 一定金額以上の購入で送料無料にするなど、購入促進の施策を考える。
- 配送時間の目安を明記し、顧客の信頼を高める。
5. 販売開始&プロモーション(SNS・ブログ活用)
すべての準備が整ったら、販売を開始し、積極的にプロモーションを行いましょう。
販売開始の流れ
- 「ストアを公開」ボタンを押して、サイトを一般公開。
- テスト注文を行い、正常に購入できるか確認。
- SNSやブログを使って告知開始。
プロモーション戦略
SNS(Instagram・Twitter・Facebook)で宣伝
- 商品の魅力を伝える投稿を定期的に行う。
- ハッシュタグを活用し、ターゲット層にリーチ。
- フォロワーを増やし、口コミを広げる。
ブログで農産物のこだわりやレシピを発信
- 「この野菜の美味しい食べ方」「生産過程のストーリー」などのコンテンツを作成。
- 商品ページへのリンクを設置し、SEO対策を強化。
メールマーケティング(メルマガ・LINE)を活用
- 新商品のお知らせや限定クーポンを配信。
- リピーターを増やすためのフォローアップメッセージを送る。
💡 ポイント
- 最初の数ヶ月はSNSとブログの発信頻度を高め、認知度を上げる。
- フォロワーの反応を見ながら、販売戦略を柔軟に調整する。
- 初回購入者向けの割引やプレゼントキャンペーンを実施すると効果的。
はやめにネットショップをつくってたくさん失敗しよう
脱サラして農業を始めるなら、「作る力」だけでなく「売る力」も磨くことが不可欠です。本記事では、オンラインショップを活用した農産物の販売について、産直ECと自前ECの比較、Shopifyを使ったショップ開設の手順まで解説しました。
販売は経験を積まなければ上達しません。最初から完璧なショップを作る必要はなく、むしろ「たくさん失敗する」ことが大切です。オンライン販売は試行錯誤しながら学べる環境が整っており、小さく始めて軌道修正を繰り返すことが成功への近道です。早めにネットショップを開設し、実際に運営する中で「何が売れるのか」「どの販促が効果的か」を体感しましょう。
特に、Shopifyを活用すれば、デザインや機能の自由度が高く、事業の成長に合わせた拡張が可能です。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、挑戦することでスキルが身につき、より安定した農業経営につながります。
小さな一歩を踏み出し、たくさんの試行錯誤を重ねながら、あなたの理想のネットショップを形にしていきましょう!



コメント