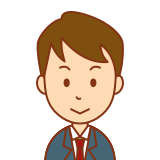
有機農業に興味があるけど、土づくりが難しそう。。。
やっぱり自作の肥料とかが必要なのかな?
こんな人のための記事です。
有機農業って本当にいろいろな流派があって、難しそうですよね。
油かすや米ぬかにもみ殻を混ぜてオリジナルのぼかし肥料をつくってる人がいたり、、、
自然の恵みを循環させるために何も与えない!という人がいたり、、、
でも私は思うのです。

まずはいちばん実績がある人の土づくりを知るべきでは!?😲
ここでいう”実績”とは、高い収益性です。
“仕事”として有機農業と向き合う以上、有機という複雑性の探求と同じくらい、
収益性も追求したい。これが私のスタンスです。
なぜならば、家族と暮らすための必要十分なお金と時間を確保し、スタッフ妥当な賃金を支払い、またその労働負荷を軽減するためには高い収益性が不可欠であるからです。
非常に高い収益性を誇る有機農場の例として、アメリカのNeversink Farmが挙げられます。
同農場はなんと0.6ha (6,000㎡=約6反)で年間35万$ (訳5,300万円 ※1$=150円換算)の収益を上げた実績があります
※出所(Neversink Farm: Making farming easier)

0.6haで35万ドル/年!?😲
さすが全米トップクラスと言われるだけのことはありますね。。。
一体どんな有機農業をやっているのだろう😏
全米トップクラスの反収を誇るNeversink FarmのConor氏は、土壌管理の徹底こそが農場経営の成功を支える基盤であると語っています。この記事では、Neversink Farmが実践する土壌管理のノウハウを徹底解説し、持続可能な農業を目指す方々に向けた具体的なアプローチを紹介します。
初心者から経験豊富な農家まで、土壌改良や管理のヒントを得られる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
土壌管理の基本概念

土壌の物理性と化学性を理解する
土壌は農作物の成長を支える基盤であり、土壌の「物理性」と「化学性」を理解することは健全な農業に欠かせません。物理性とは、土壌そのものの構造や特性を指し、例えば「砂」が多い土壌は水はけが良い一方で保水力が低く、「粘土」が多い土壌は水分をよく保持しますが、排水が悪くなることがあります。そのため、これらの特性を理解し、土壌の状態に応じた適切な改良が必要です。
Neversink FarmのConor氏は、「物理性のバランスを整えるとは、土壌が砂質すぎるか、粘土が多すぎるかを見極め、有機物を適切に追加することです」と述べています。このように、物理性の調整には有機物の投入が重要な役割を果たします。例えば、堆肥やカバークロップ(緑肥)を使用することで、土壌の粒子のつながりを改善し、適度な水はけと保水力を持つバランスの取れた土壌を作り上げることができます。
一方で、化学性は土壌に含まれる栄養素のバランスを指します。例えば、窒素、リン酸、カリウムといった主要な栄養素が過剰であったり不足していたりすると、作物の成長に悪影響を及ぼします。Neversink Farmでは、化学性を確認するために年に20回以上の土壌検査を実施しています。「土壌検査を行い、何が多すぎるのか、何が不足しているのかを把握することで、土壌のバランスを取ることができます」とConor氏は語ります。

年間20回の土壌検査はすごい😲
感覚頼りではなく、合理的なアプローチであることがわかります
物理性と化学性を調整することで、土壌中の微生物やミミズが活発に働く環境が整います。これにより、作物にとって理想的な生育環境が生まれ、収量や品質が向上します。土壌を「生きたシステム」として捉え、そのバランスを保つことが、持続可能な農業の第一歩となります。
健全な土壌がもたらす農業の利益
健全な土壌を維持することは、農業経営において多くの利益をもたらします。Neversink Farmでは、「生きた土壌」を管理することで、収益性の向上と環境保護の両立を実現しています。この手法は、すべての農業経営者にとって学ぶべきポイントです。
まず、健全な土壌は作物の収量を安定させます。物理的に良好な土壌は、根が十分に伸びるための空間と水分を提供します。また、化学的にバランスの取れた土壌は、植物が必要とする栄養素を適切な形で供給します。Conor氏は「健康な土壌を育てることで、作物が病害虫に強く、収穫量が安定します。これは年間売上40万ドルを可能にした大きな要因です」とその効果を強調しています。
さらに、健全な土壌はコスト削減にも寄与します。例えば、土壌が十分に健康であれば、化学肥料や殺虫剤の使用量を減らすことができます。Conor氏は「有機物やミミズによる自然な肥料供給を活用し、外部資材の購入を最小限に抑えています」と述べています。この結果、運営コストが大幅に削減され、収益性が高まります。
最後に、環境保護への貢献も大きな利益です。健全な土壌は炭素を保持し、気候変動の緩和に寄与します。また、土壌の浸食や劣化を防ぐことで、次世代にわたる持続可能な農業の基盤を築きます。Conor氏は「健康な土壌管理は、環境保護と収益性を両立させる唯一の方法です」と結論付けています。
土壌バランスを整えるための設計・準備
堆肥と有機物の適切な使用
堆肥と有機物は、健全な土壌を維持するために不可欠な役割を果たします。Neversink FarmのConor氏も、「堆肥と有機物を使用することで、土壌生物が活性化し、作物に必要な栄養素が自然な形で供給される」と強調しています。ここで重要なのは、堆肥と有機物の違いを明確に理解し、それぞれを適切に活用することです。
堆肥は、植物や動物由来の有機材料を分解・熟成させたもので、栄養バランスが安定しているのが特徴です。Conor氏は、「堆肥は土壌に有機物を加えるだけでなく、土壌構造を改善し、微生物の活動を支える」と説明しています。一方、有機物は、堆肥に限らず、草木の残渣や作物の根など、分解過程にある未熟な材料も含みます。これらは分解中に土壌に徐々に栄養を供給し、土壌生物の多様性を促進します。
Neversink Farmでは、堆肥を主成分としながらも、有機物の種類を多様化させることに重点を置いています。たとえば、冬にはエンドウ豆やライグラスのようなカバークロップを植え、それらを春に自然に分解させて土壌に有機物として戻しています。このプロセスは、土壌表層を保護しながら、栄養素の循環を促進する効果があります。
重要なのは、堆肥や有機物を単に追加するだけではなく、土壌の特性や作物のニーズに合わせて適切な量とタイミングで施用することです。Conor氏が「有機物を過剰に施すと、土壌中の炭素比が崩れ、微生物の働きが阻害される可能性がある」と指摘しているように、適度な管理が求められます。

有機物は多すぎてもダメなんですね😲
改良材の選び方と配合の基本
土壌改良材は、物理性や化学性を改善し、作物の成長を促進するための重要なツールです。Neversink Farmでは、Conor氏が「堆肥に加えて、適切な改良材を組み合わせることで、土壌の物理的および化学的バランスを保つ」と述べています。この節では、改良材の選択と配合における基本的な考え方を説明します。
改良材は、主に窒素、リン、カリウムといった必須栄養素を供給する役割を果たします。Neversink Farmでは、魚粉、アルファルファミール、ケルプ(海藻)などの多様な材料をミックスして使用しています。これにより、速効性のある窒素成分と、長期的に分解される成分の両方をバランスよく供給できます。「魚粉は速やかに窒素を供給しますが、羽毛ミールのような材料はゆっくりと分解され、長期的な栄養供給が可能です」とConor氏は説明します。
また、土壌の化学性を補うため、カリウムやカルシウムなどのミネラル成分を配合することも重要です。Conor氏は「カリウムは特に不足しやすく、定期的に補充が必要」と述べており、年間を通じて土壌試験を行い、正確な必要量を把握することを推奨しています。
配合時には、材料の均一性を確保するために、セメントミキサーなどのツールを活用することも有効です。この方法により、施用時の偏りを防ぎ、効率的な栄養供給が可能になります。さらに、配合した改良材を土壌表層に施用し、その上に堆肥を重ねることで、栄養素の保持力を高め、微生物の活動を促進します。
適切な改良材の選択と配合は、土壌の健康を保ち、長期的な農業の成功につながります。Neversink Farmの実践を参考に、目的に応じた改良材の利用を計画的に行いましょう。
土壌試験を活用した土壌の科学的改善
土壌試験は、農場の土壌特性を科学的に把握し、適切な改良措置を講じるための基本的な手法です。Neversink Farmでは、Conor氏が「年間20回以上の土壌試験を行い、各エリアの特性を詳細に分析している」と述べており、その重要性を強調しています。
土壌試験の主な目的は、栄養素の過不足を確認し、土壌のpHやミネラルバランスを最適化することです。Conor氏は「試験結果を基に、過剰な栄養素を排出し、不足している成分を補うことで、理想的な化学バランスを維持できる」と説明します。このプロセスにより、作物の成長に最適な環境を整えることが可能になります。
試験結果を活用する際には、エリアごとに詳細な分析を行うことが推奨されます。Neversink Farmでは、ハウスごとや畑のセクションごとに試験を実施し、「全体平均ではなく、特定のエリアに焦点を当てることで、より正確な改善が可能」としています。これは、農場全体の土壌特性が一様でない場合に特に有効です。
さらに、試験結果に基づく改善措置として、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルを調整するほか、有機改良材を適切な割合で追加することが挙げられます。Conor氏は「土壌試験を活用することで、施用する改良材の選択と量を最適化できる」と述べており、過剰施用や不足を防ぐ効果があります。
土壌試験を定期的に行うことは、持続可能な農業の基盤を築く上で欠かせません。試験結果を適切に解釈し、科学的根拠に基づいた改善措置を講じることで、農場全体の収量と品質を向上させることができます。

年間20回以上の土壌試験のコストは、
堆肥や肥料の節約効果 & 野菜の品質向上でペイできるということですね!
土壌バランスを整えるための実践的な作業・テクニック
改良材の均一な散布と効果的な取り込み方法
土壌改良材を効果的に活用するためには、均一に散布し、適切に取り込むことが重要です。Neversink FarmのConor氏も、「改良材を適切に取り込まなければ、その効果が十分に発揮されない」と述べています。このセクションでは、改良材の散布と取り込みに関する具体的なテクニックを紹介します。
まず、改良材の均一な散布が必要です。不均一な散布は、作物の成長にムラを生じさせる原因になります。Conor氏は「肥料が偏ると、成長が不均一になり、収量や品質に悪影響を及ぼす」と指摘しています。そのため、改良材を均一に散布するためには、セメントミキサーなどを使って材料を均一に混ぜるのが効果的です。また、散布の際には、手作業よりも専用の散布機を使用することで効率化が図れます。
次に、散布した改良材を土壌に取り込む方法についてです。Conor氏は、「表層に改良材を散布しただけでは効果が限定的。適度に取り込む必要がある」と強調しています。Neversink Farmでは、Tiltherを使用して土壌の表層に改良材を軽く混ぜ込む方法を採用しています。この作業は、改良材が土壌中に均等に広がり、栄養素が速やかに吸収されるのを助けます。
(Neversink Farmで使用されているTiltherはこちら)


不耕起(表層耕起)用のTiltherは日本では珍しいですね
私は輸入したティラーを使っています
さらに、改良材を堆肥や有機物と組み合わせることで、土壌生物の活動を活性化させる効果も期待できます。例えば、Conor氏は「改良材の上に堆肥を重ねて施用することで、微生物が栄養を利用しやすくなる」と述べています。この方法は、土壌の生態系全体を活性化し、長期的な土壌改善につながるでしょう。
適切な散布と取り込みは、作物の収量を最大化するだけでなく、土壌の健康を維持するための重要なステップです。これらのテクニックを取り入れ、持続可能な農業の基盤を築きましょう。
カバークロップを活用した持続的な土壌保全
カバークロップ(被覆作物)は、土壌保全と改良において極めて重要な役割を果たします。Neversink FarmのConor氏は、「冬季にエンドウ豆やライグラスなどのカバークロップを植えることで、土壌を保護し、有機物を自然に補充できる」と説明しています。ここでは、カバークロップの利点とその具体的な活用方法を解説します。
カバークロップの最大の利点は、土壌侵食の防止です。特に冬季には、降雨や雪解け水による表土の流出が懸念されます。Conor氏は「カバークロップは土壌の表面を覆い、侵食を防ぐマットのような役割を果たす」と述べています。また、これにより、土壌中の栄養素が流出するのを防ぐことも可能です。
さらに、カバークロップは有機物の供給源としても機能します。Neversink Farmでは、冬季に植えられたエンドウ豆やライグラスが春には枯れ、自然に分解されて土壌の有機物として還元されます。このプロセスは、土壌生物の活動を活性化し、栄養素の循環を促進します。「春に堆肥を追加するだけで、枯れたカバークロップがすぐに分解し、作物の栄養源として役立つ」とConor氏は述べています。
カバークロップを導入する際には、適切な種類の作物を選ぶことが重要です。例えば、エンドウ豆は窒素を固定する特性があり、ライグラスは土壌構造を安定化させる効果があります。また、これらを組み合わせて植えることで、相乗効果を得ることができます。
カバークロップは、コスト効率の良い土壌改善の手段であり、長期的な農業の持続可能性を支える重要なツールです。Neversink Farmの実践を参考に、自身の農場での活用を検討してみましょう。
No-Till農法を取り入れるための具体的技術
No-Till(不耕起)農法は、土壌を掘り返さずに作物を栽培する方法で、土壌の生態系を維持しつつ作物の収量を高めることを目指します。Neversink FarmのConor氏は「No-Till農法は効率的で環境にも優しいが、適切な技術が必要」と述べています。ここでは、No-Till農法の具体的な技術を紹介します。
No-Till農法の核心は、土壌層を逆転させないことです。Conor氏は「土壌層を保持することで、微生物や有機物が自然な形で分解・循環する環境を保てる」と説明しています。これにより、土壌生物の活動が活発になり、作物に必要な栄養素が供給されます。
技術的には、ブロードフォークを使用して土壌の通気性を確保するのが一般的です。Conor氏は「ブロードフォークは土壌層を乱さずに空気を供給できるため、No-Till農法に適している」と述べています。また、堆肥や改良材を土壌表面に施し、その上に作物を直接植える方法が推奨されています。この手法は、作業効率を高めながら、土壌の健康を維持します。
さらに、カバークロップを活用することで、土壌表面を保護し、栄養素を自然に供給することが可能です。Conor氏は「カバークロップを春に枯れた状態でそのまま活用し、その上に堆肥を追加するだけで作物の植え付け準備が整う」と述べています。この方法は、作業時間を短縮しつつ、土壌改善効果を高めるという利点があります。
No-Till農法を実践する際には、作業の効率性を確保しつつ、土壌の自然な循環を尊重することが求められます。適切なツールと手法を組み合わせることで、環境負荷を軽減しながら、高収益な農業を実現できるでしょう。
有機農業こそ緻密かつロジカルに
全米トップクラスの反収を誇るNeversink Farmの土壌管理は、想像以上に緻密でロジカルなものでした。年間20回以上もの土壌試験を圃場の細かい区画ごとに実施する姿勢は、有機農家としても稀有な存在といえるでしょう。
これまで農業を外から見ていた私のイメージでは、有機農業はオーガニックという曖昧なマジックワードや農薬の危険性を過剰に強調することでその優位性を保とうとする側面があると感じていました(もちろん全てがそうではありません)。技術の精度を高める努力が不十分なまま、販売戦略やブランドイメージだけに依存している有機農家も少なくないのではないでしょうか。
しかし、”経験”や”勘”に頼る時代は確実に変化しています。農業界ではテクノロジーやデータに基づくオペレーションが着実に進化し、これらが従来の方法論を補完し、さらには凌駕する場面も増えてきています。有機農業が理念に沿いながらも、真に顧客に価値を提供するためには、技術と経営の合理化が欠かせません。
Neversink Farmのようなファームはその理想を体現しています。「鮮度や栄養価が高い」「環境負荷が低い」「価格が妥当である」という3つの要素を兼ね備えた農産物を提供し続けるため、徹底したオペレーションと緻密な経営を実践しているのです。
私自身、有機農業に関わる者として、このような取り組みを学び、実践に活かしていかなければならないと感じています。有機農業を支える信頼と価値を築くためには、従来の方法だけでなく、緻密で論理的なアプローチを追求し続けることが重要なのです。



コメント